ダイキン給湯器 H3警報が出たら|応急処置と点検の手順解説
▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!
ダイキンの給湯器(エコキュート等)で「H3」警報が表示された場合に想定される症状と原因、応急的な再起動のやり方、点検・修理へ進む判断ポイントをまとめました。安全第一で、自己作業は取扱説明書の範囲に限り実施してください。
- H3警報が示す症状と一時的に使える機能の見極め
- リモコン表示の読み取りとエラー再現の確認手順
- 放熱不足・冷媒系・電装系など原因候補の整理
- 安全な応急処置とメーカー点検への準備
ダイキン給湯器のH3警報と原因の全体像
H3の症状と使える機能

H3は一般に「高圧側の異常を検知し、保護停止に入った」ことを示す警報として扱われます。多くのケースで新たな沸き上げ(お湯を作る動き)は停止し、機器は自己保護のために運転をやめます。一方で、貯湯タンクに既に蓄えられている残湯があれば、短時間・少流量の給湯は可能なことがあります。しかし残湯の温度や量は不確実で、混合水栓の操作や家族の同時使用によって急にぬるくなったり、逆に高温が出てヒヤリ・ハットにつながる懸念もあります。したがって入浴・追いだき・高温出湯の再開は避け、顔や手洗いなど低リスクの短時間用途に限定するのが安全です。さらに、H3発生の直前に起きた出来事(風呂運転を長くしていた、外が非常に暑い/寒い、室外機の周囲に物を置いた、停電があった等)を思い出し、箇条書きにしてメモしておくと原因の切り分けに役立ちます。機器が頻繁に停止と復帰を繰り返す状態は部品の負荷を高める可能性があるため、無理に運転を継続せず「一時停止して状況を確認する」姿勢が大切です。なお、警報を消したり強制運転を試みる行為は、想定外の圧力上昇や過熱を招くおそれがあり、取扱説明書の範囲を越える操作は避けてください。
残湯が使えるかどうかはタンク残量や水温に左右されます。無理に追いだき・高温出湯を行わないでください。
リモコン表示と確認手順

最初に行うべきは、リモコン(台所・浴室リモコン)の表示記録です。H3のコード、運転ランプの点滅状態、サブメッセージの有無、表示時刻をスマートフォンで撮影し、発生した日時と一緒に保存しましょう。次に、発生直前の使用状況(給湯量は多かったか、風呂の自動湯はり/追いだきをしていたか、シャワーは何分続けたか)と、外気条件(猛暑・厳寒・強風・積雪・直射日光の当たり方など)をメモします。停電やブレーカーの操作歴、庭木の剪定や物置の移動といった設置環境の変化も重要なヒントになります。機種によってはエラーログや自己診断の表示手順が説明書に記載されていますので、該当すれば指示に従って履歴を確認します(履歴の消去は行わないこと)。この段階では、むやみに電源を何度も入切せず、まず「一度だけ」安全な手順で再起動するか、完全停止のまま記録と観察を優先するのが無難です。再現性(同条件で短時間に再発するか)を把握できると、サポート窓口での聞き取りがスムーズになり、部品手配や訪問優先度にも好影響があります。
高圧圧力スイッチの異常

高圧圧力スイッチ(高圧保護)は、冷媒(CO₂等)の高圧側が定められた安全値を超えたときに作動し、コンプレッサ停止やシステム遮断を指示する安全装置です。実際の高圧上昇(放熱不足や冷媒循環異常)によって正しく動作する場合に加え、スイッチ自体の経年劣化、接点の焼損・固着、配線の断線・接触不良、コネクタの腐食などでも「誤検知」「復帰不能」様の挙動が起こり得ます。さらに、結露や振動、雷サージ、過去の工事時に加わった応力が遠因となることもあります。ユーザー側でできるのは「症状の記録」と「周辺状況の確認」までであり、スイッチ部の短絡、ジャンパ配線、強制復帰は重大な危険を伴います。高圧回路には圧力容器や安全弁が関与し、誤った介入は機器損傷や人身事故につながるため、分解は厳禁です。点検では、本体の異音や振動の有無、室外機の熱気のこもり、ファン回転状況、冷媒配管の霜付きや油染みなど「高圧上昇の背景」を合わせて確認します。再発性が高い、季節や時間帯で発生傾向がある、といった情報も技術者の診断に有用です。公式のエラー表示と対処の基本方針は、メーカーの取扱説明書やサポート情報を参照してください。必要に応じて、メーカー窓口に「H3で停止し、再起動で一時復帰するが再発する」「室外機周囲が高温・狭所」など具体的に伝えると適切な案内が受けられます。
高圧系統は安全弁・圧力部品を含みます。分解・短絡やジャンパは重大事故の原因になります。
放熱不足(汚れ・積雪・日射)

室外機が十分に放熱できないと、高圧側の圧力が上がりやすくなり、H3などの保護停止につながります。代表例はアルミフィンの汚れ・目詰まりです。キッチン排気や道路粉じん、海沿いの塩分、庭木の花粉・綿毛、洗濯物の繊維くずなどが層になって付着すると、風が通っていても熱が抜けにくくなります。加えて、室外機の前後左右や上部が物置や植栽、フェンスで囲われている「狭所設置」では、吐き出した温風が再び吸い込まれる「再循環」が起きやすく、コンデンサ温度が上がって高圧上昇の引き金になります。猛暑期の直射日光や、無風・無日陰の炎天下、ベランダのコンクリ床からの照り返しも負荷を増やす要因です。寒冷地では逆に積雪が吸気・排気を塞ぎ、溶けた霜水が凍結して氷塊になり、フィンやファンに干渉して回転を阻害することがあります。
ユーザーができる対策は、安全確保のうえでの「清掃」と「風の通り道の確保」です。電源OFF・乾燥状態で、柔らかいブラシや低圧の水で表面の埃を優しく落とし、フィンを曲げないように作業します(高圧洗浄機や強い薬剤は避ける)。室外機の前面・背面・側面・上方に十分な離隔を取り、可動のパネルやカバーで吸排気を妨げない配置に見直します。直射が強い場合に日よけを設置する際は、屋根やシェードが風の通りを阻害しない位置・高さ・角度とし、温風の再循環を招かないよう排気側に「逃げ」を作ることが肝心です。積雪時は周辺の雪壁を取り除き、排水経路が凍って氷柱にならないよう水はけを確保します。近接する物干し、DIY棚、ゴミストッカー、鉢植えなど一時的に置いた物が熱交換を妨げていないかも点検しましょう。これらの基本を押さえるだけでも、再発率が目に見えて下がることがあります。ただし、清掃後もすぐにH3が再発する場合は、放熱不足以外の要因(冷媒循環や電装系)を疑い、無理な連続運転は控えてください。
清掃は電源OFF・乾燥状態で、柔らかいブラシと低圧の水で行いましょう。フィンの折れや水のかけ過ぎに注意。
冷媒不足・漏えいのサイン

冷媒が不足している、あるいは微小な漏えいが続いていると、運転開始直後は一見正常でも、負荷が高まる場面(連続シャワー、風呂自動湯はり、猛暑・厳寒)で循環が乱れ、保護停止に至ることがあります。視覚的なサインとしては、配管継手やバルブ近傍の「油じみ」や「埃が油で固着して黒く見える」箇所、低圧側配管の不自然な霜付き、プシューという持続的な微音、起動直後のコンプレッサ異音や振動の増加などが挙げられます。とはいえ、CO₂など高圧冷媒を扱う回路は極めて高い圧力がかかるため、ユーザーがバルブや継手に触れたり、漏えい箇所を石けん水で探す、トルクをかけ直す、といった行為は厳禁です。できることは、状況の記録(気温・負荷条件・再発までの時間)、異常音の動画、油じみの写真を残し、使用を控えめにして早期に点検を依頼することに尽きます。
技術者の点検では、圧力・温度の同時測定、質量流量やサブクール/過熱度の推定、リーク検知器や窒素耐圧試験など体系的な診断が行われます。単純な「ガス補充」で一時的に回復しても、漏えいが残っていれば短期間で再発しますし、機器や環境への負荷も無視できません。再発のタイミング(暑い午後だけ、追いだき時だけ、数日おき等)や、室外機周囲の熱気こもりとの相関を共有すると、原因の切り分けが速くなります。なお、配管の押しつぶしや急激な曲げ、施工後の外力(自転車や物置の接触)、小動物による被覆損傷など、設置後に生じた物理的ダメージも疑う価値があります。いずれにせよ、冷媒系は資格作業の領域であり、ユーザーは観察と安全確保に徹し、強制運転や頻繁なリセットは避けてください。
基板・配線・コネクタ不良

制御基板や配線・コネクタの不具合は、放熱や冷媒とは別系統でH3相当の停止を誘発することがあります。例えば、基板上のリレー接点の摩耗や半田クラック、コンデンサの劣化による電圧不安定、コネクタの微腐食・緩み、ハーネスの屈曲部での断線、筐体内の結露・湿気、虫の侵入や小動物による噛み傷などです。これらは温度変化や振動で症状が出たり引っ込んだりする「断続的トラブル」になりやすく、同一条件でのみ発生するケースも少なくありません。ユーザーの段階では、焦げ臭や異音、パネル外側から見える焼け痕の有無、筐体や周辺からの漏水跡、有害な薬剤や塩分ミストに晒されていないか、といった外観と環境要因の確認に留めます。パネルを開けての通電点検や部品交換は感電・短絡の危険があるため避けてください。
技術者による診断は、目視・導通・絶縁抵抗・電源系のリップル測定、センサー・アクチュエータの入出力確認、熱ストレス(温冷での再現試験)など段階的に進みます。落雷後や大規模停電の復帰直後に発生し始めた事例では、サージによる基板損傷の可能性が高く、交換が最短解となることもあります。再発性が高い場合は、いつ・どの操作で・何分後に止まるのか、前兆音やランプ挙動はどうだったか、動画を添えて伝えると、部品の当たりをつけやすく訪問回数を減らせます。予防策としては、屋外側の防水・防塵の配慮、配線の擦れ対策、ネズミ忌避、雷の多い地域でのサージ保護(建物側の適切なアースや避雷設備の点検)など、設置環境の健全化が有効です。また、分電盤の専用回路で他の大電流機器と同時投入にならないよう運用を見直すだけでも、電圧降下による誤作動の予防につながります。いずれのケースでも、無理な再起動の繰り返しは故障の悪化を招くため、記録を整理して点検に臨むのが得策です。
ファン異常・霜付着と外気温

ファンモーターの回転不良や羽根の損傷、異物の噛み込みは、室外機の吸排気性能を直ちに低下させ、放熱不足を招いて高圧側の圧力上昇を引き起こします。特に冬季の厳寒時は霜が熱交換器に付着しやすく、除霜運転(デフロスト)が正しく行われないと短時間で熱が抜けず、H3相当の保護停止に至る場合があります。霜取り水の排水が不十分で足元に氷塊が形成されると、ファンカバーや羽根に干渉し、こすれる音や回転低下の原因になります。加えて、強風が一方向から当たり続ける立地では、吐き出し空気が戻り込みやすく、風の偏りが除霜制御を乱すこともあります。ユーザー側の観察ポイントは、電源OFF・安全確保のうえで「羽根の欠け・歪み」「手で軽く回したときの引っ掛かり」「異物付着」「周囲の氷・雪壁」「運転中の異音(こすれ音・周期的な唸り)」といった外観・聴診に限られます。無理に氷を工具で割る、羽根を矯正する、カバーを外して通電点検する行為は危険です。設置改善としては、排水の逃げ道を確保し、雪の吹き溜まりを避ける柵や簡易風除けを「吸排気を妨げない位置」に設置する、室外機下に適切な架台を用いて積雪面から離隔を取る、といった対策が有効です。霜が厚く積もる環境では、定期的に周囲の雪を取り除くことに加え、除霜中に温風が再循環しないレイアウト(背面や側面の空き)を確保するだけでも再発を抑えられます。
ダイキン給湯器のH3警報|対処と点検・修理の手引き
再起動手順(遮断器OFF→ON)

H3は一時的な外的要因(瞬間的な放熱不足、電圧変動など)で作動することもあり、正しい手順での再起動で復帰するケースがあります。推奨される流れは次の通りです。①給湯・風呂運転を停止し、水栓を全て閉じる。②リモコンの運転スイッチをOFF。③貯湯ユニットの漏電遮断器、または分電盤の専用ブレーカーをOFFにして10〜30秒静置(内部回路の放電・制御の再初期化のため)。④ブレーカーをONに戻し、リモコンをON。⑤小流量で給湯を試し、異音・異臭・振動・再発の有無を確認。ここで重要なのは「再起動は多用しない」ことです。短時間で再発する、復帰してもすぐ停止する、異音や焦げ臭がある、といった兆候があれば、以降の操作を中止して点検を依頼します。また、停電復帰直後は電源系が不安定な場合があるため、周辺の大電流機器(IH、エアコン、乾燥機等)と同時起動を避ける運用も一案です。再起動の結果は時刻とともに記録し、「何分後・どの運転で再発したか」を具体的に残しておくと、技術者が高圧上昇のトリガー条件(外気温、負荷、風路状況)を推定しやすくなります。なお、機種固有の復帰手順やエラー確認モードがある場合は、必ず取扱説明書の指示を最優先してください。
頻繁な電源ON/OFFは推奨されません。再起動は1回程度に留め、再発する場合は使用を中止して点検依頼へ。
再発時の対応と使用中止

再起動後にH3が短時間で再表示される、あるいは運転中に「金属がこすれるような音」「周期的なうなり」「焦げ臭いにおい」がする場合は、機器保護と安全のために速やかに使用を中止します。続行はコンプレッサや基板、圧力部品への負荷を増大させ、損傷・漏えい・発煙のリスクを高めます。まずは電源をOFFにし、室外機周辺の障害物・積雪・落ち葉・氷を安全に撤去できる範囲で処置し、以後は通電を控えます。そのうえで、家族の生活動線(入浴・洗濯・炊事)への影響を最小化する代替手段を手配し、点検の訪問予定に合わせて「設置写真」「エラー表示の写真」「異音の動画」「発生時の外気条件メモ」を用意します。漏水・漏電・焼損の痕跡が目視される場合や、ブレーカーが直ちに落ちる場合は、触れずに周囲の安全を確保して連絡します。再発が特定の時間帯(午後の直射が強い時間、深夜の氷点下)や特定の運転(風呂自動湯はり、シャワー連続使用)で起こるなら、その条件を具体的に伝えることが診断の近道です。自己判断での強制運転・リセットの連打・基板の抜き差しは避け、あくまで観察と記録に徹することが、結果的に修理コストとダウンタイムを抑える最善策となります。
サポート連絡の準備事項
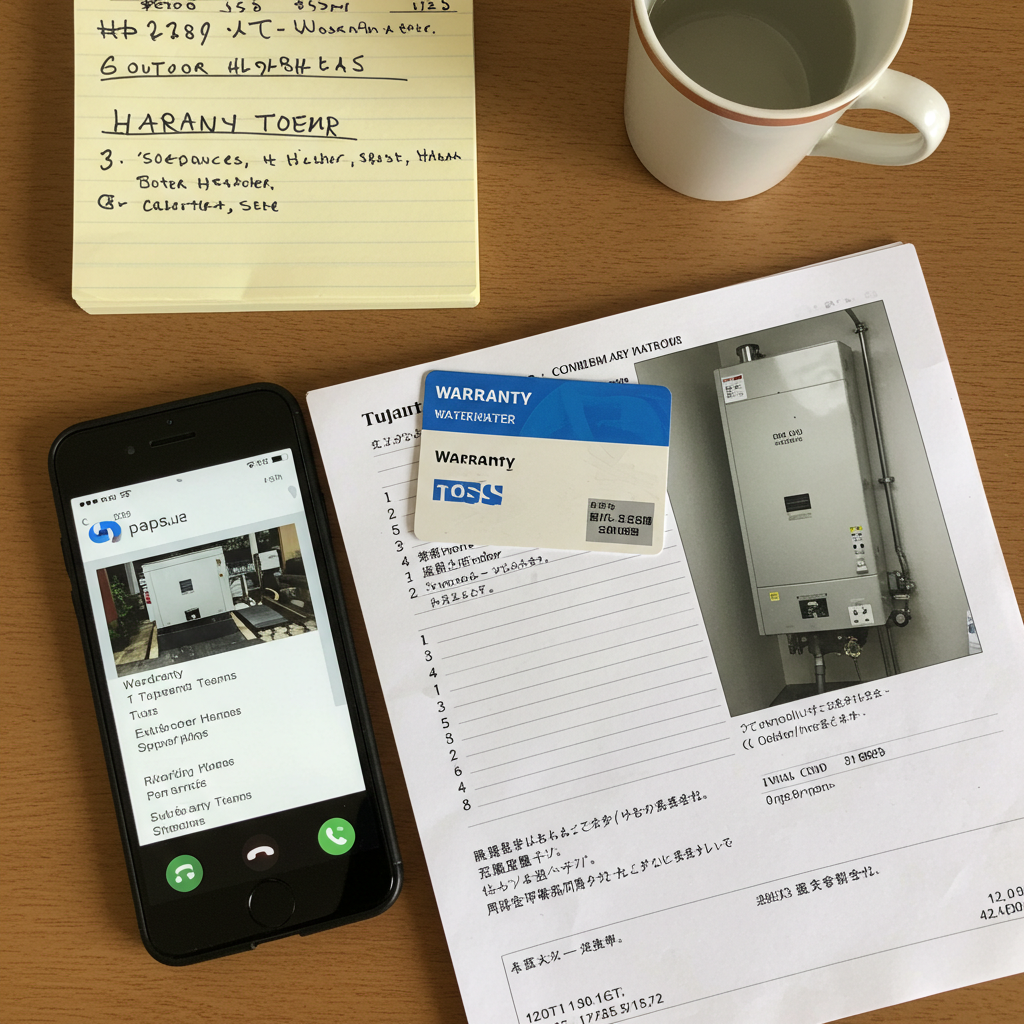
点検・修理の初動を素早く、正確に進めるためには、連絡前の情報整理が重要です。まず機器の「型式」「製造番号」「設置年」および「設置場所の状況(戸建て・集合住宅、ベランダ・地上、狭所・直射・塩害地域等)」を把握します。つぎに、H3発生の「日時」「使用中の運転モード(給湯・風呂自動・追いだき)」「外気条件(気温・直射・積雪・強風)」「直前の操作(長時間シャワー、浴槽の高温足し湯、停電復帰など)」を時系列でまとめ、リモコン表示の写真や短い動画を添えられると理想的です。再起動を試したなら「実施回数」「復帰の有無」「再発までの時間」「異音・異臭・振動の有無」を明記します。施工店やメーカー窓口へは、状況を簡潔に箇条書きで伝えるとヒアリングがスムーズになり、必要部品の事前手配や優先度判断がしやすくなります。訪問当日は、室外機周囲の作業スペースを確保し、電源・水道・敷地内通路の安全を整えておくと、診断と作業の時間短縮につながります。保証の有無(メーカー保証・延長保証・住宅設備保証)や購入経路(ハウスメーカー・量販店・設備店)も合わせて確認しておくと、費用負担と修理可否の判断が明確になります。なお、窓口では「H3で停止し、再起動で一時復帰するが負荷をかけると再発」「室外機は狭所で夏は直射が強い」「低温時に霜や氷が多い」といった環境条件も具体的に伝えると、放熱・冷媒・電装のどこに重点を置くべきかの当たりがつけやすくなります。公式の取扱説明書や修理相談窓口はメーカーサイトの型式ページから辿れます。
| 項目 | 具体例・メモ |
|---|---|
| 機種名・製造番号 | 本体銘板・保証書を確認 |
| エラー表示 | H3・表示時刻・点滅状態の写真 |
| 発生状況 | 給湯・風呂運転の有無、外気温、積雪 |
| 再起動の有無 | 実施回数と結果、再発までの時間 |
| 設置環境 | 室外機周囲のスペース・障害物・直射 |
| 施工・点検履歴 | 直近の清掃や部品交換の有無 |
保証期間中か延長保証の有無も確認しましょう。症状の写真・動画は診断の助けになります。
清掃と設置環境の見直し

H3の予防・再発抑制には、ユーザーが可能な範囲での清掃と熱環境の是正が効果的です。大原則は「電源OFF・乾燥状態・安全確保」。まず室外機の吸気側(背面フィン)と吹出し側(前面ファン)の障害物を撤去し、前後左右および上方に十分な離隔を確保します。アルミフィンの清掃は、柔らかいブラシで埃を撫で落とし、必要に応じて低圧の散水で汚れを流す程度に留め、フィンの曲がりや水のかけ過ぎ、高圧洗浄機や強アルカリ洗剤の使用は避けます。油煙や塩分の多い環境では、付着しやすい面を重点的に点検し、落ち葉・花粉・綿毛が溜まる季節は頻度を上げます。猛暑期の直射対策としては、通風を阻害しない位置に日よけを設け、熱い排気が再循環しないよう屋根・シェードの奥行と高さを調整します。寒冷期は、霜取り水の排水経路を確保し、氷柱や氷塊がファン・フィンに干渉しないよう足元の水はけを管理します。物干し台、物置、植栽、DIY棚、ゴミストッカー、アウトドア用品など、一時的に置いてしまいがちな品が吸排気の道を塞いでいないかも定期チェックを。ベランダ設置では、床面の照り返しや囲いによる熱気こもりが強いため、風の抜け道を意識した配置に見直します。これらの小さな是正の積み重ねが、コンデンサ温度上昇の抑制につながり、高圧保護の作動頻度を下げる実効策になります。
高所・不安定な足場での作業、薬剤を使う高圧洗浄は専門業者に相談してください。
作業時の安全上の注意

給湯機は「電気」「圧力(冷媒)」「水」が交差する機器であり、ユーザーが安全に実施できる作業には明確な限界があります。次の原則を守ってください。①高圧冷媒回路・高圧スイッチ・コンプレッサ・電子基板の分解や短絡、通電状態での点検は行わない。②清掃や周囲整理は必ず電源OFF・乾燥状態で実施し、濡れた手での操作や雨天・降雪時の無理な作業を避ける。③異音(こすれ・周期的唸り・金属音)や焦げ臭、発煙、漏水が見られたら直ちに停止し、以降は触れずに安全を確保して連絡する。④脚立やベランダ手すりなど高所・不安定な足場での作業は避け、転落・挟まれ事故のリスクを最小化する。⑤子どもや高齢者の火傷予防として、残湯利用時は混合水栓の急な温度変化に注意し、高温出湯や追いだきの使用を控える。⑥再起動は原則1回のみ、結果を記録し、短時間で再発する場合は運転を継続しない。⑦落雷後・停電復帰直後は電源系が不安定なことがあるため、他の大電流機器との同時投入を避ける。⑧自作の覆い・囲い・風除けは吸排気を妨げない設計にし、可燃物を近接させない。これらの遵守により、二次被害や症状の悪化を防ぎつつ、専門家による安全な診断と修理にバトンをつなげられます。安全を最優先に、取扱説明書の範囲を超える行為は実施しないことが肝要です。
まとめ|ダイキン給湯器H3警報
- H3警報は保護停止を示すため無理な運転再開を避け安全を最優先する
- 残湯が使えても追いだきや高温出湯は控え症状の再現性を確認する
- リモコン表示は写真で記録し発生時刻や外気条件もメモして診断に活かす
- 室外機の放熱不足は汚れ積雪日射狭所が要因になり清掃と離隔で改善を図る
- 高圧圧力スイッチの劣化や接点不良は交換前提で自己分解は厳禁と心得る
- 冷媒不足や漏えいが疑われる兆候は油滲み霜付き異音で専門点検を依頼する
- 基板配線コネクタの不具合は振動湿気雷などが遠因となり専門診断が必要
- ファンの回転不良や霜付着は除霜制御と設置条件を見直し再発を抑制する
- 再起動は遮断器のOFFから短時間待機後にONとし多用せず結果を記録する
- 再発や異臭異音がある場合は使用を中止し早期に点検の手配を行う
- 連絡時は機種名製造番号エラー写真設置環境履歴を整理し伝達を簡潔にする
- 清掃や日よけなどユーザー作業は取説範囲に留め危険作業は依頼に切り替える
- 保証や延長保証の適用可否を確認し費用と時間の目安を事前に共有する
- 停電や環境変化がきっかけのH3は再発要因の除去と監視で様子を見る
- 総じてダイキン給湯器のH3警報は原因切り分けの整理と安全確保が最優先となる
よくある質問(FAQ)
H3警報は何を意味しますか?
一般に高圧側の異常上昇を検知した際の保護停止を示します。原因は放熱不足、冷媒循環不良、電装系不具合など多岐にわたるため、無理な再運転は避けてください。
一度だけリセット(再起動)しても大丈夫ですか?
取扱説明書の範囲で遮断器OFF→10〜30秒→ONの再起動を「1回のみ」試すのは目安として可です。短時間で再発・異音・焦げ臭がある場合は使用中止し、点検を依頼してください。
残っているお湯(残湯)は使ってもいいですか?
少量・短時間の用途に限定すれば可能な場合がありますが、温度変化が急になることがあるため入浴や追いだき、高温出湯は控えてください。火傷防止を最優先に。
自分でできる対処は何がありますか?
電源OFFのうえで室外機周囲の清掃・離隔確保、積雪や落ち葉の撤去、直射・熱気の再循環対策など設置環境の是正です。冷媒回路や基板への介入は行わないでください。
冬にだけH3が出ます。原因は?
霜付着や除霜水の凍結による放熱低下、雪壁による吸排気阻害が典型です。排水の逃げ道を確保し、雪・氷の干渉を除去して風の通りを改善しましょう。
停電やブレーカー復帰後にH3が表示されました
電源系の一時不安定や復帰直後の外気・負荷条件が重なって保護が作動することがあります。再起動を1回だけ試し、再発する場合は使用中止のうえ点検へ。
どの情報を伝えて修理を依頼すれば良いですか?
型式・製造番号、H3表示の写真、発生日時と運転状況、外気条件、再起動の結果、設置環境(狭所・直射・積雪)を時系列でまとめて伝えると初動が速くなります。
修理費用の目安は?買い替え判断は?
故障部位で大きく変動します。高圧スイッチ・基板・冷媒系などは診断が前提です。設置年数や保証の有無、主要部品の供給状況を踏まえ、見積りで比較検討してください。
保証は使えますか?
メーカー保証・延長保証・住宅設備保証の適用範囲と期間に依存します。保証書と購入書類を確認し、症状・写真と合わせて窓口へ相談してください。
リモコンのエラー履歴は確認できますか?
機種によっては自己診断・履歴表示が用意されています。該当手順は取扱説明書の「エラー表示」章をご参照ください。履歴の消去は行わず記録を残しましょう。
室外機の清掃はどこまで自分でやって良いですか?
外装とフィン表面の軽い埃落とし、周囲の障害物・落ち葉の撤去に留めます。高圧洗浄や薬剤洗浄、分解は行わないでください。
公式の情報はどこで確認できますか?
取扱説明書や修理相談の窓口はメーカー公式サイトから参照できます。必要に応じて型式で検索し、正規情報を確認してください。ダイキン公式サポート
参考・出典
- 資源エネルギー庁「月々の電気料金の内訳」 – 基本料金・電力量料金・燃料費調整・再エネ賦課金の公式解説
- 資源エネルギー庁「燃料費調整制度とは」 – 調整単価の計算方法と上限の考え方
- ダイキン「エラーコード検索」 – 給湯機のエラーコード(H3等)に関するメーカー公式情報
▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!



















