ノーリツ 給湯器 音がする症状別の原因と修理費用
▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!
ノーリツ給湯器から「音がする」「異音がする」と感じたとき、音の種類や発生条件によって考えられる原因と対処は異なります。本記事では、お湯出し時・追いだき時・点火/停止時・強風/雨天などの場面別に、キーン音・ゴー音・ブーン音・カタカタ音・ポコポコ音の代表例を整理し、点検手順や修理・交換の目安費用をガイドします。断定は避け、一次情報や一般的な施工基準を参照しつつ、安全確保を最優先とした判断の考え方をまとめました。
- 症状別(場面・音の種類)に原因候補を整理
- 自分でできる初期チェックと注意点を確認
- 修理に発展しやすい部品と費用目安を把握
- 交換判断や近隣騒音対策の考え方を理解
ノーリツ給湯器で音がする原因
- お湯出し時の異音
- 追いだき時の異音
- 点火・停止時の音
- 強風・雨天のノイズ
- キーン・高周波音の要因
- ゴー・ブーン音の要因
お湯出し時の異音

蛇口を開けてから数秒〜十数秒のあいだに目立つ「ゴー」「ブーン」「キーン」は、燃焼の立ち上がりと送風量の追従制御、そして給水圧の変動が重なる過渡現象で顕在化しやすいと考えられます。まず候補となるのが送風機(ファン)由来の機械音と、熱交換器や筐体板金の固有振動が一致して生じる共鳴です。羽根車の微小な偏芯や汚れの付着、吸気経路の塵・虫の残留はバランスを崩し、回転数の立ち上がり域で特に唸りが強くなります。水側では混合水栓カートリッジ、逆止弁、減圧弁が半開付近でチャタリング(微振動)を起こし、金属質の「ジー」「チー」という連続音に感じられる場合があります。集合住宅・高圧給水では夜間に給水圧が上がる傾向があり、同じ開度でも流量が変化して音量が増すことがあるため、時間帯による差も記録しておくと切り分けに有効です。屋外壁掛けでは背面下地の剛性不足や取付金具の緩み、外壁材の空洞などにより固体伝搬音が増幅され、室内に低音が響くことも少なくありません。観察の要点は(1)別の蛇口でも同様か(2)湯温設定・流量を変えると音質が変化するか(3)天候・時間帯との相関があるか、の3点です。いずれかで改善が見られれば局所要因の可能性が高く、改善が乏しければ機器本体側(ファン、固定、筐体)へのアプローチが現実的です。急に音が大きくなった、焦げ臭・煤・排気変色があるといった安全上の兆候が重なるときは、使用を中止し点検を手配する判断が推奨されます。
追いだき時の異音

浴槽の追いだき中に「ポコポコ」「ゴボゴボ」といった断続的な水音、あるいは「ウー」という低い共鳴が続く場合、第一に循環配管系への空気混入や気泡滞留を疑います。浴槽水位が循環口より低い、循環アダプターやフィルターの汚れで吸い込みが不安定、配管ルートの高所で気泡が抜けにくい、といった条件が重なると、気泡の出入りとともに周期音が発生しやすくなります。床暖房併用機では暖房回路のエア噛みやポンプのベアリング摩耗で唸り音が増幅し、追いだき運転と同時に共鳴を引き起こすこともあります。まずは浴槽を基準水位まで満たし、循環フィルター・ストレーナを清掃してから再現確認を行い、症状が弱まるかを観察します。改善が乏しければ、循環アダプターのガタ、配管固定バンドの緩み、分岐マニホールドの振動、コンデンシング機特有のドレン配管の滞留による気泡音も候補です。運転停止直後に音が強まる場合は、残留熱やドレンの動きが関与していることがあり、配管勾配や通気条件の見直しが改善の近道となるケースが多く見られます。なお、気泡が多い状態での連続運転は循環ポンプに負担を与えるため、無理に継続せず原因の切り分けと対策を優先します。
点火・停止時の音

点火の瞬間に「ボッ」「パチッ」という小音が出るのは一般に機構上の一過性現象ですが、連続する「バチバチ」や金属打音、停止直後に大きな振動が生じる場合は、燃焼空気量とガス量のバランス不良、点火電極・ケーブルの劣化、熱交換器や筐体内部の固定不良等を疑う余地があります。炎の不安定(揺れ・異常な炎色)、煤の付着、排気口の変色、焦げ臭など安全リスクを示す兆候が伴う際は、直ちに使用を止め換気を確保したうえで点検依頼が望まれます。ベランダ等の半屋外では風の巻き込みにより排気が滞留しやすく、音が反響して大きく感じられることもあります。サービス依頼時に「いつ・どの操作で・どんな音が・何秒続くか」をリモコン時刻と合わせて記録・共有すると、診断が効率化します。DIYで行うのは外装ねじの増し締めや周辺清掃程度にとどめ、内部の分解・改造・吸排気部材の変更は行わないのが安全です。
強風・雨天のノイズ

強風下の「ヒュオー」「ゴー」は、給排気トップやダクトでの風切り音、逆圧・負圧変動による空力騒音が主因です。トップの向きや高さが周囲の手すり・壁面と作る狭いスリットに一致すると、笛吹き現象のような共鳴が発生し、音が増幅されます。雨天時にだけ強まる「ポコポコ」「コンコン」という音は、コンデンシング機のドレン経路で滞留・通気不良が生じ、気泡が周期的に移動することが背景にあります。点検の着眼点は(1)トップ周囲の障害物・ネット・飾り板の干渉(2)ダクト接続部・フードのガタ(3)ドレン配管の勾配・横引き長さ・封水トラップの適合、の3点です。ベランダで風抜けが悪い場合は排気の滞留と温度上昇で渦が生じ、音がこもって室内側に回り込むことがあるため、メーカー適合の風向板や防雪部材の活用が選択肢になります(ただし安全距離・仕様の遵守が前提)。施工後に天候依存で音が増えた場合は、設置位置・向き・周囲構造の影響が大きい可能性があり、現地での離隔再確認と部材固定の見直しが有効です。
キーン・高周波音の要因
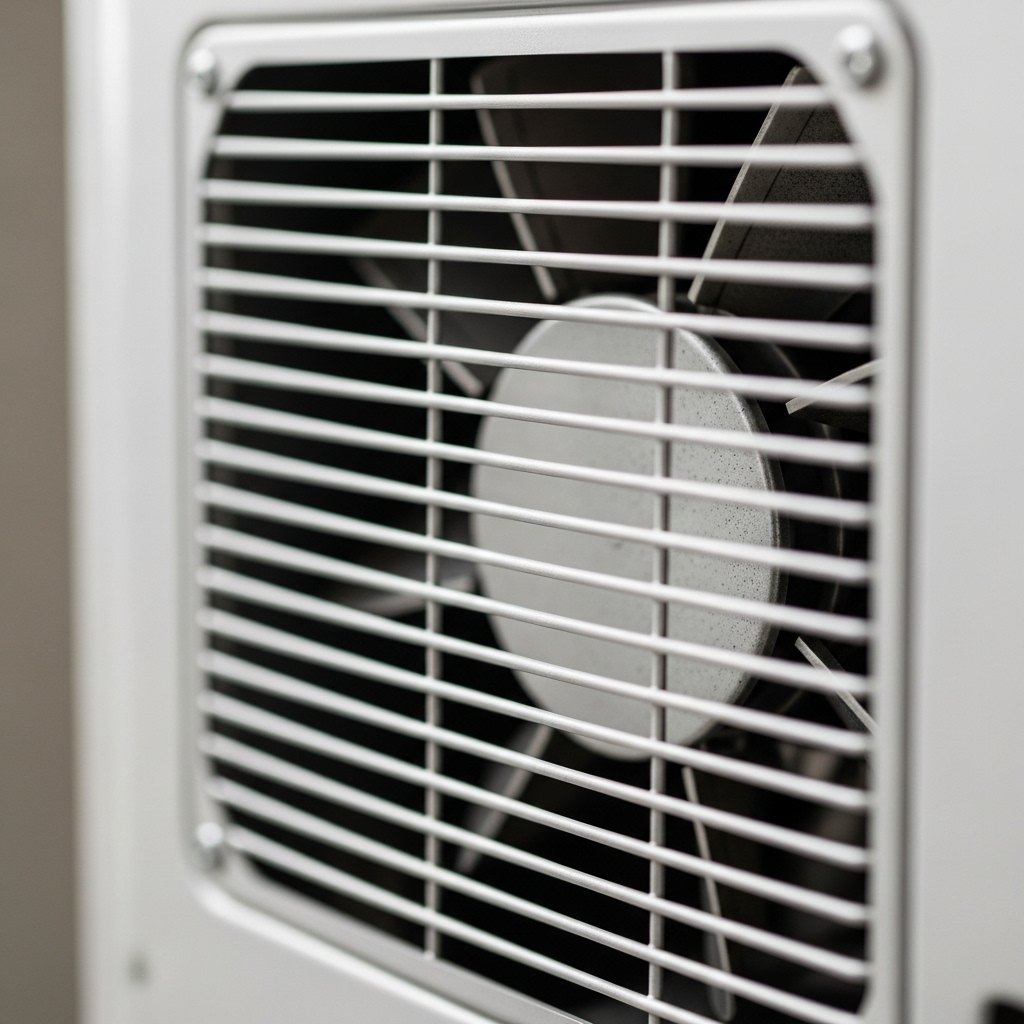
「キーン」と耳障りに響く高周波成分は、ファンモーターのベアリング摩耗や軽微な偏芯、ダクト・板金の固有振動、基板上のインダクタ(いわゆるコイル鳴き)などが複合して生じます。周波数帯の特性上、空気伝搬の減衰が小さく、窓ガラスや壁面で反射・定在波が起きると実際の音圧以上に強く感じられます。観察では(1)給湯負荷(風量)に比例して音が増減するか(2)本体の一部を軽く押圧すると音が変わるか(3)雨風・時間帯との相関があるか、を確認します。押圧で変化するなら固定クリップやビスの緩み・当たり修正、防振材の介在で改善が見込めます。負荷に追従して甲高くなるならファン消耗やエアフロー乱れが示唆され、分解清掃やファン交換(専門作業)が現実的です。集合住宅では室内の限られた位置のみで強く感じることがあり、厚手カーテン・ラグの併用や家具配置の工夫で体感が緩和する場合があります。
ゴー・ブーン音の要因

低〜中周波の「ゴー」「ブーン」は、ファン回転と熱交換器・筐体・外壁を介した固体伝搬の組み合わせで顕在化します。背面下地の空洞、取付金具の微小なガタ、配管クランプ不足は増幅要因です。対策の基本は(1)取付ビスの増し締め(2)配管クランプの追加・位置最適化(3)本体と外壁の間に樹脂スペーサーや防振パッドを適切に介在、の三点。年数を経た機器では吸気経路への砂塵・虫の付着で羽根車バランスが崩れ、回転数帯により唸りが顕著になるため、内部清掃やファン交換が必要となるケースがあります。狭い通路や囲われたベランダでは反響対策より振動源対処(固定・バランス・交換)が効果的で、根本原因に沿った是正が近道です。急激な悪化や異物接触が疑われる場合は運転を控え、点検を優先してください。
ノーリツ給湯器の音がする対処
- カタカタ・ビビり音対策
- ポコポコ水音と配管内空気
- ウォーターハンマーの予防
- 自分でできる初期チェック
- 修理判断と費用目安
- まとめ:ノーリツ給湯器で音がする
カタカタ・ビビり音対策

「カタカタ」「ビビり」は外装板金・配管・ダクト・支持金具の微小な隙間や干渉が原因となることが多く、局所を特定して固定と当たりを修正するのが王道です。具体的には、化粧カバーや前面パネルのかみ合わせ調整、リベット・ねじの増し締め、板金端部と接触面のクリアランス確保、防振材(薄手ブチルや発泡体)のポイント介在が効果的です。配管は長い片持ちやエルボ直後が振動腹になりやすく、クランプ追加や緩衝材を挟むだけでも体感が変わります。ベランダでは手すり・床との二次共鳴に注意し、支持金具の剛性不足が疑われる場合は金具交換や補強を検討します。DIYは外装・周辺の固定強化に限定し、内部への介入や吸排気ルートの変更は安全上の理由から避けてください。再発防止として、定期的な増し締め、虫侵入防止網の清掃・固定、風で揺れる付属物の撤去も合わせて実施すると安定します。
ポコポコ水音と配管内空気

対策の第一歩は基準水位の確保と循環フィルター清掃です。循環口より十分高い水位を保ち、フィルター・循環アダプターの汚れやガタを除去すると、吸い込みの安定とともに気泡混入が減ります。ドレン配管に起因する気泡音は、横引きを短くし十分な勾配を確保、通気不足の解消、封水トラップの適合確認で低減できます。給湯配管側の空気混入が疑われる場合は、家中の蛇口を順番に開けてのエア抜きを実施し、急開閉は避けて圧力波を抑えます。運転停止後に音が強い場合は、残留熱で発生した気泡やドレン溜まりの移動が関与していることがあり、停止→一定時間後の挙動も観察ポイントです。改善しないときは、配管取り回しや高低差の見直し、循環ポンプ・マニホールド・アダプターの点検といった機器側診断へ進むのが合理的です。
ウォーターハンマーの予防

蛇口や電磁弁の急閉止による「ドン」という打音はウォーターハンマー(圧力波)で、配管固定不足、高水圧、弁類の作動点不一致が背景にあります。予防の基本は(1)減圧弁で適正圧へ整える(2)配管アレスターを要所に設置(3)長い片持ち・エルボ直後・器具近傍の固定強化(4)劣化した混合水栓カートリッジを交換、の4点です。マンションの高圧給水では夜間に目立ちやすいため、生活面では閉止操作をゆっくりにするだけでも体感が改善します。なお、給湯器内部の安全弁・電磁弁は機能上の作動音を伴うため完全な無音化は困難ですが、異常に大きい打音、新築・リフォーム後に急増した打音は配管系の条件変更が原因のことが多く、管理会社・施工業者・メーカーの三者連携で現地確認するのが最短経路です。
自分でできる初期チェック

安全を最優先に、ユーザーが実施しやすいチェックを段階化します。(1)リモコンのエラー表示と時刻を確認し、発生時刻・天候・操作内容をメモする。(2)吸気口・排気口の塞がり、虫・落ち葉・粉塵の付着、トップやフードのガタを目視点検し、周辺清掃を行う。(3)浴槽の循環フィルター・ストレーナを水洗い、循環口の異物除去と水位調整。(4)本体外装ねじ・配管化粧カバー・支持金具の増し締め、指で軽く押圧して音が変わる箇所の特定。(5)別の蛇口・時間帯・設定温度で再現性を確認し、系統起因か器具起因か切り分ける。焦げ臭・煤・排気の逆流感・CO警報の作動など危険兆候があれば即時停止・換気・点検依頼が原則です。ガス・燃焼部・基板への介入、吸排気部材の改造は行わず、外装・周辺の確認に留めます。
修理判断と費用目安

異音が消耗品劣化や固定不良に起因する場合、多くは修理で改善が期待できます。代表的には、ファン摩耗・羽根車バランス不良はファン交換や内部清掃、点火時の連続スパーク・不安定燃焼は電極・ケーブル・燃焼系調整、コイル鳴き疑いは基板交換が検討対象です。配管のビビり・共鳴は増し締め・クランプ追加・防振材介在で低コスト対応が可能なケースもあります。修理か交換かの分岐は、(1)設置10年以上(部品供給・他部位劣化リスク)(2)主要部品の複数不良(同時交換で高額化)(3)修理見積が新規導入との差額に接近(省エネ・静音のメリット含む)(4)設置条件起因の騒音を新機種の静音設計と併せて是正したい、などが重なる場面です。交換時は、後継機の静音仕様(ファン径・流路形状・制御)に加え、取付面補強・防振パーツ同時施工・ドレン配管取り回し最適化をセットで設計すると体感効果が高まります。見積取得では、症状の再現動画・写真・時系列メモを共有し、作業範囲(内部清掃の有無)、純正部品・保証、出張費・再訪費を明文化して比較してください。
| 症状/部位 | 代表的な原因 | 対処 | 費用目安(税込) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高周波・キーン音 | ファンモーター摩耗、共振 | ファン交換・防振調整 | 2.5万〜5.5万円 | 機種・設置状況で差 |
| 連続のゴー/ブーン | ファン・熱交換器共鳴 | 固定見直し・部品交換 | 2万〜7万円 | 複合要因で上振れ |
| 点火時のバチバチ | 点火系・燃焼安定不良 | 電極/ケーブル交換調整 | 1.5万〜4万円 | 煤・排気経路も点検 |
| カタカタ・ビビり | 板金/配管の固定不足 | 増し締め・防振材追加 | 0.5万〜2万円 | 軽微なら応急で可 |
| ポコポコ水音 | 配管内空気・ドレン溜まり | エア抜き・勾配是正 | 0.5万〜2.5万円 | 循環口清掃で改善例多 |
| 打音(ドン) | ウォーターハンマー | 圧力調整・アレスター | 1万〜3万円 | 集合住宅は要協議 |
| 循環系の唸り | ポンプ軸受摩耗 | 循環ポンプ交換 | 3万〜6万円 | 床暖併用機で発生 |
| 金属打音 | 熱膨張・固定緩み | 支持・クリアランス調整 | 0.8万〜2.5万円 | 取付面の剛性影響 |
| 基板由来のノイズ | コイル鳴き等 | 基板交換(必要時) | 2.5万〜6万円 | 症状説明と再現が重要 |
まとめ:ノーリツ給湯器で音がする
- 音の種類と発生場面を記録し原因を絞り込む
- 強風や雨天など外的条件の影響を見極める
- 循環フィルター清掃と適正水位で水音を抑える
- 固定ねじの増し締めと防振材でビビりを減らす
- ウォーターハンマーは圧力調整と緩衝器で予防
- 別蛇口や別時間で再現し系統か局所か判定する
- 焦げ臭さや煤の兆候があれば使用を中止する
- 排気口の塞がりや虫侵入の有無を点検する
- ファンやポンプの劣化は早めの交換で予防する
- 取付面の剛性と背面の当たりを最適化する
- 費用は部品と環境で幅があり見積を比較する
- 設置年数と不具合数で修理か交換を選択する
- 近隣配慮のため夜間の大音量運転を避ける
- 管理会社や施工業者と情報共有を行う
- 安全最優先で無理な分解や改造は行わない
FAQ(ノーリツ 給湯器の音がする)
Q. 夜だけ給湯器の音が大きく感じます。故障でしょうか?
A. 夜間は給水圧や周囲の騒音環境が変わり、同じ作動音でも大きく感じることがあります。まず時間帯を変えて再現性を確認し、取付金具や配管クランプの緩み、ベランダの反響条件を点検します。急に増大した・金属打音が混じるなどの変化があれば点検依頼を検討します。
Q. 点火時の「ボッ」「パチッ」という音は異常ですか?
A. 多くは着火時特有の一過性の音で、単体では直ちに異常とは言えません。ただし連続的なバチバチ音、異常燃焼を疑うにおい・煤・排気口の変色が伴う場合は使用を中止し換気のうえ点検をご検討ください。
Q. 追いだき中の「ポコポコ」水音を止めるには?
A. 浴槽の水位を循環口より十分高く保ち、循環フィルターと循環アダプターを清掃します。改善しなければ配管内の空気滞留やドレン配管の勾配・通気不良が疑われるため、現地での取り回し確認が有効です。
Q. 「キーン」という高い音が続きます。原因は何が考えられますか?
A. ファンモーターの摩耗・偏芯、筐体やダクトの固有振動、基板部品のコイル鳴きなど複合要因が考えられます。外装の増し締めや当たり修正で改善する場合もありますが、回転数に比例して甲高くなるならファン交換などの修理が現実的です。
Q. 強風や雨の日だけ「ゴー」「ヒュオー」と鳴ります。対策は?
A. 給排気トップやダクトの風切り音、ドレン滞留による気泡音の可能性があります。トップ周辺の障害物・ネットの干渉、固定の緩み、ドレンの勾配・通気を点検します。専用の風向板などは適合品を使い、独自改造は避けてください。
Q. 蛇口を急に閉めると「ドン」と鳴ります。ウォーターハンマーですか?
A. 急閉止時の打音はウォーターハンマーの典型です。減圧弁による適正化、配管アレスター設置、配管固定の強化、劣化した混合水栓カートリッジの交換が抑制策となります。集合住宅では系統条件に依存するため管理会社・施工業者と相談が有効です。
Q. 自分でできる安全な確認はどこまでですか?
A. 外装ねじ・配管化粧カバーの増し締め、周辺清掃、吸気・排気口の目視確認、循環フィルターの水洗い、別蛇口・時間帯での再現確認までは一般的に実施しやすい範囲です。内部の分解やガス系・基板・吸排気部材の改造は行わないでください。
Q. 修理費はどのくらい見込めばよいですか?
A. 症状や機種・地域で幅がありますが、外装のビビり調整は数千〜数万円、点火系調整は1.5万〜4万円、ファン関連の交換・調整で2万〜7万円程度の事例が見られます。正式な費用は現地診断と見積比較でご確認ください。
Q. 設置から何年経ったら交換も検討すべきですか?
A. 一般的に10年前後が一つの目安とされます。主要部品の複数不良や高額見積、静音・省エネの改善を重視する場合は交換も選択肢です。取付面の補強や防振対策、ドレン取り回し最適化を同時に行うと体感改善が期待できます。
Q. どのタイミングでメーカーや業者に連絡すべき?
A. 焦げ臭・煤・一酸化炭素警報の作動、排気の逆流感、急な大音量化、金属打音が続く等の安全リスクが疑われる場合は即時停止・換気のうえ点検をご依頼ください。症状の動画・発生条件・時間帯の記録を共有すると診断が早まります。
▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!



















