ノーリツ給湯器 燃焼ランプ点滅は何の合図か対策まとめ徹底解説
▶ 関連記事: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!
ノーリツの給湯器で燃焼ランプが点滅するときは、燃焼の開始・継続に関わる制御や安全装置が作動している合図である場合があります。本記事では「ノーリツ 給湯器 燃焼 ランプ 点滅」を主軸に、意味の整理から一次確認、エラー表示別の見方、家庭でできる点検範囲と依頼判断までを体系的に解説します。断定は避け、公式情報と安全性を最優先に整理します。
- 燃焼ランプ点滅の基本的な意味と正常時の例
- 最初に行う安全確認とガスメーター復帰
- リモコン表示の読み方と主要エラーの傾向
- 家庭で可能な点検と修理依頼の判断材料
ノーリツ給湯器の燃焼ランプ点滅
この件に関する総合的な情報は、給湯器の復帰ボタンが点滅しない原因と自分でできる対処法まとめで詳しく解説しています。
- 症状と点滅の意味(正常時の点滅も)
- 最初に確認:電源と元栓
- ガスメーター遮断の復帰(公式手順)
- リモコン表示の見方とリセット
- エラー11/111 点火不良
- エラー120 炎検出不良
- エラー90 燃焼不具合
症状と点滅の意味(正常時の点滅も)

ノーリツ給湯器の燃焼ランプ(炎アイコン・運転表示灯など)が点滅するときは、機種固有の制御ロジックに従って「着火準備中」「安全確認中」「温度制御のための燃焼断続」「異常検知による停止」など複数の状態を示すことがあります。まず押さえておきたいのは、点滅=必ずしも故障とは限らない点です。たとえば夏場の高い給水温では、設定湯温との差が小さく、熱交換器を保護しながら温度を安定させるために、短い燃焼と停止を繰り返す制御が働きます。この際、炎アイコンが断続的に点滅し、使用感としては「お湯が出たり弱まったりする」ように感じる場合があります。一方で、点滅の周期が速い、同時にリモコンへエラー番号が表示される、点火音がしてもすぐ消える、排気口付近から異音・煤の付着が見られるといった兆候がある場合は、燃焼や検出系の異常、給排気やガス供給の不具合が疑われます。点滅の意味は取扱説明書に定義されているため、まずは機種型式を確認し、点灯・点滅・消灯の違い、連続/断続のリズム、エラー表示の有無を整理します。加えて、同じ環境・同じ設定で再現するか、天候(強風・豪雨・低温)、使用条件(同時に他機器を使用、シャワーの急な開閉)で変化するかを記録すると、原因切り分けの精度が上がります。まとめると、①正常な温度制御に伴う点滅、②安全装置動作を含む一時停止、③故障コードを伴う異常、の三層で観察し、エラー表示の有無と併せて次の手順へ進むのが安全です。
最初に確認:電源と元栓

異常を疑う前に、誰でも安全に確認できる一次チェックを行います。第一に電源系です。コンセントの抜け・タコ足配線・延長コードの劣化・ブレーカーの作動履歴を確認し、雷雨や停電後は主電源の再投入(数十秒オフ→オン)を実施します。給湯器リモコンの時刻がリセットされている、照明が一時的に暗くなったなどの兆候があれば、電源品質の揺らぎが関与している可能性があります。第二にガス・水の元栓です。台所下・屋外メーターバルブ・機器直近の手動ガス栓が「開」になっているか、給水元栓や止水栓が充分に開いているかを確かめます。第三に周囲環境の安全確認です。ガス臭・焦げ臭・カバーの溶け・煤の付着・水漏れ痕・配管の結露/凍結・動物や昆虫の侵入痕(巣・クモの糸)を目視し、異常所見があれば使用を中止して換気を確保します。屋外機は風雨や紫外線の影響を受けやすく、コンセントやケーブルの被覆劣化、端子の腐食が点火不良の引き金になることがあります。また、同時に複数のガス機器(コンロ・暖房)を使用すると、家庭内のガス圧が一時的に下がり点火しにくい状況が生じます。これらの基本点検を行っても症状が再発する、もしくはエラー番号が即時に再表示される場合は、内部保護機能が働いている可能性が高く、無理な連続再試行は避けてください。
ガスメーター遮断の復帰(公式手順)

地震感知・長時間連続使用・瞬時的な過大流量などが起きると、マイコンメーター(ガスメーター)の安全機能が遮断を行い、給湯器は点火試行の点滅を示しながらも燃焼に移行できなくなります。まずメーターの表示窓を確認し、赤色ランプの点滅や「ガス止」等の表示がないかを確認します。遮断が表示されていれば、周囲にガス臭がないこと、火気が近くにないこと、換気が確保されていることを前提に、復帰ボタンの押下→待機(数分間)→点滅停止の確認という基本手順で復帰操作を行います。復帰後にすぐ再遮断する場合は、配管漏えい・機器不具合・風の影響による燃焼異常など潜在要因が残存している可能性があるため、使用を控えて販売店やガス事業者へ相談してください。地震後は余震が続く間、再遮断が起きやすいほか、給排気系のズレや外壁の変形によってドラフトが乱れ、立消えが発生するケースもあります。復帰操作はあくまで安全が確認できる状況でのみ行い、少しでも不安や異常所見(異音・異臭・煤)があるときは、居室の窓を開けて退避し、専門窓口の指示を仰ぐのが原則です。メーターの位置が高所・狭所にある場合や手順が不明な場合は、無理に触れず、案内に従ってください。
リモコン表示の見方とリセット

ノーリツ給湯器のリモコン表示は、運転状態とエラーの手掛かりを提供します。まず現在の表示が「湯温」「残り時間」などの通常画面か、「エラー番号」「点検お知らせ」かを切り分けます。点検お知らせ(例:88/888)は経年点検の推奨であり、直ちに危険を示すものではないと案内されることがあります。一方で、11や120、90などの番号が点滅・点灯している場合は、燃焼関連の保護が働いた兆候と受け止め、無理な連続再試行を避けるのが安全です。基本操作として、運転スイッチをオフにして数十秒待ち、再度オンにする「運転入切」、本体の主電源プラグを抜き差しする「再投入」(感電・濡れに注意)、メイン・サブリモコン双方の表示確認とケーブルの緩み確認を行います。再投入後に「即時同じエラーが再表示」されるなら、単なる一時的な誤検知よりも「再現性のある要因」が疑われます。逆に、強風や入浴の同時使用など特定条件でのみ出る場合は、環境要因の可能性が高まります。ここで重要なのは、リセットはあくまで「状態を初期化して観察するための手段」であり、根本原因の解消ではないという点です。操作ごとに、外気温や風、使用時間、給水温、同時使用機器の有無といった状況をメモしておくと、後の点検や修理の際に診断時間の短縮につながります。また、表示の見方や操作手順は機種やリモコン型番で異なるため、手元の取扱説明書に従う姿勢が安全です。
エラー11/111 点火不良

エラー11(または111)は点火不良を示す代表的な表示で、点火プラグの火花が飛んでも炎が安定しない、あるいはそもそも着火に至らない状況を指すことがあります。家庭で確認できる範囲としては、ガス栓とメーターの開状態、ガスメーター遮断の有無、他のガス機器の同時使用状況、給気・排気の確保が中心です。屋外機では、前面や下面の開口付近に落ち葉・虫・埃が溜まり、着火直後の空気量が不足して失火するケースが見受けられます。また、強風でドラフトが乱れると、点火直後に炎が吹き飛ばされるような挙動となり、結果として点火不良と判定されることがあります。連続的に「カチッ」という点火音がしても燃焼音へ移行しない場合、ガス圧低下や電極ギャップのずれ、電装基板や点火トランスの弱りといった要因が絡むこともあります。自力での分解清掃や電極調整は感電・漏えい・一酸化炭素事故のリスクが高く推奨されません。できる範囲は、風が強い日の使用を一時見合わせる、排気口・周囲の遮蔽物を取り除く、フィルタやストレーナの清掃、電源品質(たこ足・延長コードの見直し)といった安全な外周対策に留め、再発するなら速やかに販売店やメーカーへ点検を依頼します。設置から年数が経っている場合は、点火電極やガスバルブの劣化が背後にあることも少なくないため、修理と更新の費用対効果を比較検討する姿勢が現実的です。
エラー120 炎検出不良

エラー120は「燃えているはずの炎をセンサーが検出できない」または「検出値が安定しない」と解釈される表示です。炎検出は一般にフレームロッド(炎電流)やフォトセンサーで行われ、汚れ・湿気・錆・配線接触不良などにより検出感度が下がると発生しやすくなります。雨天後や湿度の高い日のみ再現する、長時間停止後の初回起動でだけ出やすい、といったパターンは典型例です。家庭でできる安全な確認は、周囲の乾燥・換気の確保、排気口の詰まり除去、屋外コンセントまわりの防水状態や漏電ブレーカー履歴の確認などに限られます。内部のセンサー清掃や位置調整は燃焼系の分解を伴い、わずかな誤組付けでも立消えや不完全燃焼の危険があるため、自己作業は避けるべきです。強風の直撃や排気の吹き戻しによって炎が揺さぶられた結果、センサーが断続状態と解釈して120を出すこともあり得ますので、設置環境の見直し(防風対策、離隔の確保、周囲障害物の撤去)は有効です。再発が続く、点火後すぐに消える音がする、煤の付着が目立つ、異臭がするなどの兆候がある場合は、燃焼調整や部品交換(センサー・バーナー・ファン・基板)が必要となる可能性が高く、早期の点検依頼が結果的に安全と費用の両面で合理的です。
エラー90 燃焼不具合

エラー90は「燃焼が設計どおりに安定していない」ことを総合的に示すコードで、単一部位の故障というよりは、入出力(ガス・空気・排気・水量)や制御(センサー・基板・ファン回転)に関わる複合要因で生じやすいのが特徴です。たとえば、熱交換器やバーナーの目にスス・ホコリが堆積していると混合気の流れが乱れ、火炎が長く伸びたり短くなったりして検出値がふらつきます。さらに、給気不足や排気の吹き戻し、強風の乱流、周囲障害物によるリサーキュレーション(排気が再び吸い込まれる現象)も不安定化の典型要因です。家庭で試せる安全な切り分けとしては、①使用環境の整備(排気口前0.5m以上の離隔確保、植栽や物品の移動、強風時の使用を控える)、②他のガス機器との同時使用を一時停止してガス圧の変動を抑える、③シャワー・洗面などの急激な流量変化を避け一定吐水で観察する、④フィルターストレーナの清掃と十分な流量の確保、が現実的です。これでも再発する場合は、ファンモータ回転数のふらつき、イオン検出の感度低下、ガス比例弁の作動不良、熱交換器の目詰まりなど専門計測が必要な領域に踏み込みます。煤の付着や黄色い炎、焦げ臭、異音(唸り・金属共振)などの兆候があれば、自己判断は避けて使用を中止し、点検を依頼するのが安全です。とりわけ設置後10年超では複数部品の経年劣化が重なりやすく、部品交換と本体更新の費用対効果を比較する判断が実務的です。
ノーリツ給湯器の燃焼ランプ点滅の対処
- エラー01/02 サーミスタ
- 排気不良と排気口の点検
- 強風・設置環境の対策
- 吸気フィルター清掃方法
- 石油機の灯油切れ対策
- 修理費用と本体交換の目安
- ノーリツ給湯器の燃焼ランプ点滅まとめ
エラー01/02 サーミスタ
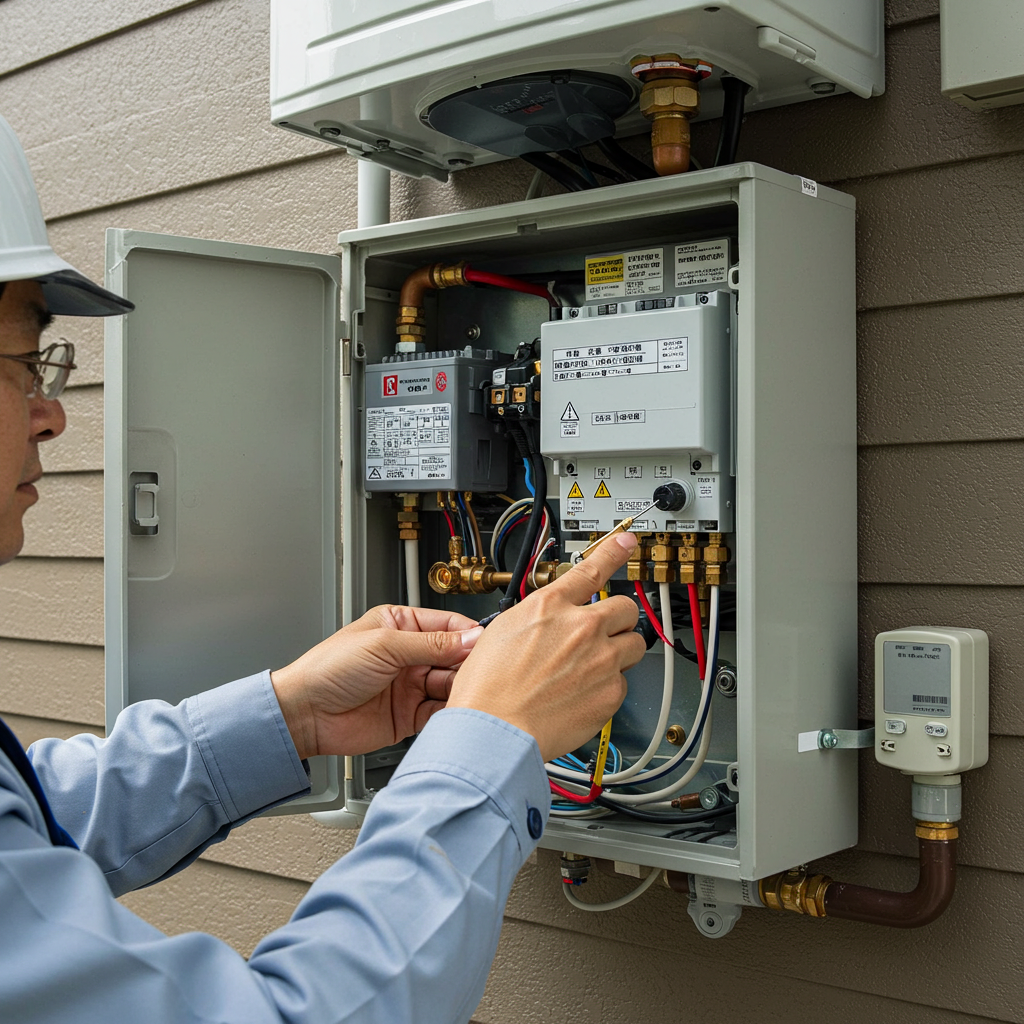
サーミスタは入水・出湯・熱交換器などの温度を電気抵抗値として検出し、燃焼量や安全制御の基準となる重要部品です。エラー01/02は、その検出が「あり得ない値」「急激な変化」「断線・短絡相当」と解釈された際に表示されることがあります。実態としては、配管内のスケールやゴミによる熱応答の遅れ、ストレーナの目詰まりによる流量低下、端子の酸化やコネクタの接触不良、湿気侵入による抵抗値の不安定化などが関与します。ユーザー側で安全にできるのは、機器手前の給水フィルター(ストレーナ)を止水のうえで取り外し、異物を除去して十分に水洗い・乾燥して復旧すること、吐水量を「極端に絞らない」運用に変えて温度制御に余裕を持たせることです。冬場は水温が低く、同じ出湯温度でも必要燃焼量が増えるため、微小流量で高温設定といった条件が重なると偏差が拡大し、サーミスタ系のエラーが誘発されやすくなります。再発が続く、温度ムラが顕著、湯温が設定に達しない、表示と体感が一致しないといった症状が重なる場合は、サーミスタ自体の劣化や配線の損傷、基板側のA/D変換の異常などが疑われ、部品交換・点検が現実解です。分解を伴う測定・交換は漏水や感電のリスクを含むため自己作業は避け、型式と症状、再現条件(時間帯・流量・設定温度)を整理して依頼すると診断がスムーズです。
排気不良と排気口の点検

燃焼ガスが適切に屋外へ排出されないと、センサー群は安全側へ寄せて燃焼を停止し、結果として燃焼ランプの点滅や各種エラーが表示されます。屋外壁掛け型では、排気口の前方・左右・上方の離隔を確保することが基本で、植栽・物置・自転車・洗濯物・積雪・氷結・落ち葉・虫の巣などが想定以上に障害となります。まずは排気口を目視し、黒ずみや煤、白い粉末、結露の滴り跡など「流れの乱れ」を示すサインがないかを確認します。次に、強風時や特定風向(建物のコーナー部、狭小通路、庇の下)でのみ症状が出るかを観察します。これらは排気が建物壁で跳ね返って再吸込み(リサーキュレーション)を起こす典型条件です。対策としては、臨時的には可動物の撤去や洗濯物の位置変更、恒久的には防風板の設置、排気口向きの変更、近接物の配置換えなどが挙げられます。屋内設置・排気筒タイプでは、継手の外れ・たわみ・腐食、鳥害対策網の閉塞、鋭角曲げ過多などがドラフト低下の原因です。煙道温が十分に上がらない初期運転時に立消え気味となる場合もあるため、暖機の挙動も観察ポイントです。排気経路の分解・改造は法規やメーカー条件に関わるため、DIYでの加工は厳禁です。点検では「前面0.5m・左右上下の離隔」「高さ方向の障害」「季節ごとの周辺環境変化」をチェックリスト化し、写真を残して業者へ共有すると、環境要因の切り分けが短時間で行えます。
強風・設置環境の対策

屋外設置の給湯器は風向・風速・建物形状の影響を強く受け、強風時には排気が機器前面へ吹き戻されたり、給気側へ回り込んだりして燃焼が不安定になりやすくなります。とくに建物の角や狭い通路、ベランダ手すり付近、庇の下などは乱流が発生しやすく、同じ風速でも立消えや炎揺れ(炎長が伸縮する現象)が起きやすい配置です。症状が「風の強い日だけ」「特定の季節風の時だけ」再現するなら、環境起因の可能性を優先して検討します。対策の基本は、①排気が滞留・反射しない離隔の確保(前方・左右・上方の空間確保)、②周囲の可動物の撤去(物干し・植栽・収納品)、③防風・整流の工夫(メーカーが許容する範囲での防風板や風除けの追加)、④機器向きの検討(吹き戻しを受けにくい方向へ変更)です。臨時対応としては、強風警報時の高温・微小流量運転を避け、なるべく一定流量で短時間の使用にとどめることで立消えリスクを下げられます。恒久対応を検討する際は、取付け場所の壁面・床面からの反射、近接する障害物の配置、隣家の壁や塀の位置関係を写真で記録し、施工店に現地で評価してもらうのが安全です。なお、排気フードや排気方向の改造、排気筒の延長・曲げ追加などは法規・メーカー条件に抵触する場合があるためDIYは厳禁です。結果として、強風の直撃を避けた配置へ見直し、風の通り道を整理し、離隔を確保することが、燃焼ランプ点滅やエラーの季節的再発を抑える現実的なアプローチとなります。
吸気フィルター清掃方法

室内設置型やFF式の一部機種には吸気経路にフィルターがあり、埃や繊維クズの付着で空気流量が不足すると、燃焼が不安定になり点滅・エラーが誘発されます。清掃の前には必ず運転を停止し、主電源を切り、必要に応じて止水を行います。次に取扱説明書を参照し、前面カバーの開け方とフィルターの位置を確認します。取り外したフィルターは、柔らかなブラシや掃除機で表面の埃を除去し、汚れが強い場合はぬるま湯で軽く押し洗いします。強い洗剤・シンナー・溶剤は繊維を劣化させるため使用しません。水洗い後は十分に乾燥させ、変形や破れがないことを確認してから元に戻します。清掃頻度は設置環境により異なりますが、換気扇の多用やペット・繊維くずの多い場所では短期で目詰まりしやすく、月1回程度の点検・清掃が目安になります。再組付け時はパッキンの浮きや隙間がないか、ダクト接続が確実かを目視で確認し、隙間からの空気漏れや誤吸い込みは燃焼制御の乱れを招くため要注意です。清掃後に症状が改善しない、すぐに再発する、運転音が異常に大きい、出湯温度が不安定といった兆候が残る場合は、ファン回転や熱交換器、バーナー部の汚れなど別要因が疑われます。分解を伴う内部清掃は感電や一酸化炭素事故のリスクがあるため自己作業は避け、型式・設置環境・再現条件を整理して点検を依頼するのが安全です。
石油機の灯油切れ対策

ノーリツの石油給湯機では、灯油切れや水分混入、長期未使用後の配管内エア噛みが原因で、点火不良・燃焼不安定・燃焼ランプ点滅が起こることがあります。まず、タンク残量を目視で確認し、灯油が古い(長期保管)・濁りがある・底部に水が溜まっている可能性がある場合は交換・水抜きを検討します。補給後に失火が続く場合は、機種の手順に従って送油ラインのエア抜きを行います(止水・電源オフ・耐油手袋・ウエス準備など安全確保が前提)。ストレーナ(フィルター)が詰まっていると燃料供給が間欠になり、着火してもすぐ消える現象につながるため、止栓のうえで取り外し、ゴミやスラッジを除去して復旧します。寒冷期にはタンク内の水分が凍結し、流量が低下することで失火が誘発されることがあるため、結露対策や凍結防止(保温・残量管理)も有効です。なお、電磁ポンプやノズル、燃焼ヘッドの清掃・交換は高温部位・燃料漏えいの危険を伴うためユーザー作業の対象外です。エア抜きやフィルター清掃を行っても改善しない、燃焼時に異音・黒煙・刺激臭がする、運転が短時間で停止する、といった場合は直ちに使用を中止してください。燃焼系の不具合を放置すると不完全燃焼や機器損傷に発展するリスクがあるため、症状・使用燃料の状態・補給や清掃の実施歴を整理し、販売店またはメーカーの点検を依頼するのが合理的です。灯油は品質劣化が早いため、少量ずつの補給と定期的なタンクメンテナンスを習慣化することで再発を予防できます。
修理費用と本体交換の目安

給湯器の修理費用は「出張診断+部品代+作業工賃」の合算で構成され、症状と機種によって幅があります。一般的には出張診断だけで数千円台からの費用が生じ、さらに交換が必要な部位によって合計額が大きく変動します。たとえばファンモーターや燃焼系の部品(点火トランス・電極・炎検出関連)は作業時間も伴うため、軽微なセンサー交換より高額になりやすい傾向です。熱交換器の目詰まりやバーナーの強清掃は、分解・洗浄・組付け・燃焼調整の工程を含み、作業時間が長くなればその分の工賃が加算されます。部品の供給状況も重要で、設置後10年を超える機器ではメーカーの保守部品が順次供給終了となる場合があり、可及的な在庫で対応できないと総合修理の成立性が下がります。ここで判断材料となるのが「修理費の見込み」と「残存寿命のバランス」です。既に複数の部位で劣化徴候がある、季節によって別種のエラーが交互に出る、異音や出湯不安定が併発しているといったケースでは、単発修理が短期的な延命にとどまりやすく、次の不具合で再度の出張費と工賃が必要になる可能性があります。逆に、設置からの年数が浅く、設置環境も良好で、単一部品の自然故障と見做せる場合は修理が費用対効果に優れます。交換検討の目安としては、①設置10年超、②安全系エラーの再発、③修理見積が本体更新費の3〜5割以上、④居住形態や生活動線上での停止リスクを許容できない、のいずれかに該当する場合が挙げられます。更新の利点は、保証のリセットと高効率機への移行に伴う省エネ性能の向上、最新の安全制御・低騒音化の恩恵を受けられる点です。施工時には既設配管・電源・リモコン配線の健全性確認、給排気経路の見直し、離隔や防風の対策を合わせて行うと、同様トラブルの再発抑制につながります。見積比較の際は、本体価格だけでなく「標準工事範囲」「追加工事の要否」「撤去費用」「保証年数と範囲」を同一条件で確認し、将来の保守コストも含めて総額で評価するのが合理的です。
ノーリツ給湯器の燃焼ランプ点滅まとめ
- 燃焼ランプ点滅は異常断定ではなく状態表示の一種であり状況観察が重要
- 強風や外気温水温など周囲条件で発生しうるため再現条件の記録が有効
- まず電源とガス栓と給水元栓を順に確認し安全最優先で落ち着いて対応
- ガスメーター遮断時は表示を確認し復帰操作後の再遮断有無を確認する
- リモコンのエラー番号は手掛かりで断定材料ではない点を前提に判断する
- エラー十一は点火不良で給気排気とガス供給の整合性確認が基本となる
- エラー百二十は炎検出不良で湿気汚れ配線接触など外周要因も疑う
- エラー九十は複合要因で離隔確保や流量安定化と専門診断が有効である
- サーミスタ異常時は流量確保とストレーナ清掃で応急対応が可能である
- 排気口の離隔確保と障害物除去で吹き戻しや立消えの予防効果が高い
- 強風直撃設置では防風対策と機器向き見直しで再発低減が期待できる
- 吸気フィルターの定期清掃は不安定燃焼の主要リスクの一つを抑制する
- 石油機は灯油品質管理と送油ラインのエア抜きで失火再発を抑えられる
- 異臭異音煤の付着など危険兆候があれば即時停止し専門点検を依頼する
- 十年超機は部品供給と再発率を勘案し修理より更新が合理的な場合がある
FAQ(ノーリツ給湯器の燃焼ランプ点滅)
Q. 燃焼ランプが点滅するのは故障ですか?
A. 故障とは限りません。着火準備や温度制御に伴う断続燃焼でも点滅します。エラー番号表示の有無、点滅の再現条件(強風・流量・設定温度)を確認し、異臭や異音があれば使用を中止してください。
Q. エラー11(111)が出たときの最初の対処は?
A. 電源の再投入、ガス栓・メーターバルブの開状態、他ガス機器の同時使用有無、給気・排気の確保を安全範囲で確認します。再発する場合や点火音のみで燃焼に移行しない場合は点検依頼が安全です。
Q. エラー120(炎検出不良)は何が原因ですか?
A. 炎は出ていてもセンサーが検出しにくい状態(汚れ・湿気・配線接触不良・強風による炎揺れ)で起きやすいです。内部清掃や調整は危険を伴うため自己分解は避け、環境確認後に点検を依頼してください。
Q. エラー90(燃焼不具合)はどう切り分けますか?
A. 入出力(ガス・空気・排気・水量)や制御の複合要因です。排気口前の障害物除去、強風時の運転回避、ストレーナ清掃、同時使用機器の抑制などを試し、再発するなら専門診断が必要です。
Q. 点検お知らせ「88/888」は故障ですか?解除できますか?
A. 故障通知ではなく点検時期の案内です。安全上は使用を中止し、販売店やメーカーへ点検相談してください。勝手な解除や内部設定の変更は推奨されません。
Q. ガスメーターが遮断しているかの見分け方は?
A. メーターの表示窓の点滅表示や「ガス止」などの状態表示で判断します。ガス臭がない・換気が確保できる状況で、表示に沿って復帰操作を行い、再遮断する場合は使用を控えて相談してください。
Q. リモコンのリセットで直る場合と直らない場合の違いは?
A. 一時的な条件(強風・流量変動・湿気)が要因なら再投入で回復することもあります。即時に同じエラーが再表示される場合は再現性のある不具合の可能性が高く、無理な再試行は避けてください。
Q. 強風の日だけ点滅・停止します。設置の見直しは必要?
A. 建物の角・狭小通路・庇下など乱流が起きやすい場所では再発しやすく、離隔確保や防風対策、機器の向きの見直しが有効です。排気部材の改造は行わず、施工店に現地評価を依頼してください。
Q. 吸気フィルターの清掃は自分でできますか?
A. 取扱説明書の手順に従い、電源オフのうえ取り外し・水洗い・乾燥・確実な復旧を行えば可能な機種があります。破れや変形があれば交換が必要です。内部の分解やダクトの改造は行わないでください。
Q. 石油給湯機で点滅します。灯油が原因のことはありますか?
A. あります。灯油の劣化・水分混入・エア噛みで送油が不安定になり失火が起きます。補給後はエア抜きとストレーナ清掃を安全に実施し、改善しない・黒煙や異臭がある場合は使用を中止してください。
Q. 何年使用したら交換を検討すべき?
A. 一般に設置10年を超えると複数部品の劣化と保守部品の供給状況から、再発率と費用の観点で本体交換が選択肢になります。安全系エラーの再発や修理見積が高額な場合は特に検討してください。
Q. どのタイミングで使用を中止し、連絡すべきですか?
A. ガス臭・焦げ臭・黒煙・異常音・排気口の煤付着・エラーの連続再発などがある場合は直ちに使用を中止し、換気のうえ販売店・ガス事業者・メーカーへ連絡してください。自己修理は行わないでください。
参考・出典
-
総務省消防庁「食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故防止について」
- ガス消費設備使用時の換気義務や不完全燃焼・一酸化炭素中毒事故の事例と注意喚起をまとめた公式資料。 -
日本ガス株式会社「マイコンメーター復帰方法」
- マイコンメーター(ガスメーター)遮断時の一般的な復帰手順と安全上の注意点を図解で解説したページ。 -
ノーリツ「給湯機器:エラー表示【11】が点滅」
- ノーリツ給湯器のエラー11表示の意味、想定される故障部品、修理の必要性や費用の目安を説明するメーカー公式FAQ。
▶ さらに詳しく: 給湯器の故障症状と原因別の対処法を完全解説!



















