給湯器の異音キュルキュル|危険度の目安とNG対応・正しい初期対応
給湯器の異音(キュルキュル)は、配管の共振やポンプ・ファンの摩耗、流量の不安定化など複数要因が重なることで生じるとされています。本記事では「給湯器 異音 キュルキュル」の検索意図に沿って、危険度の考え方、避けるべき対応、自分でできる初期確認、修理費用と交換判断の要点を中立的に整理します。分解や調整が必要な作業は専門業者に相談してください。
この記事で分かること
- キュルキュル音の主因と危険度の目安
- シャワーや追い焚き時に鳴る仕組み
- 自分でできる安全確認とNG対応
- 修理費用と交換判断の基本方針
目次
- 1 給湯器の異音(キュルキュル)の原因と見分け方
- 2 給湯器の異音キュルキュル対策
- 2.0.1 Q1. 給湯器のキュルキュル音は放置しても大丈夫?
- 2.0.2 Q2. まず自分で確認できる安全な対処は?
- 2.0.3 Q3. シャワーのときだけキュルキュル鳴るのはなぜ?
- 2.0.4 Q4. 冬だけ異音が増えるのは故障?
- 2.0.5 Q5. 正常なファン作動音と故障のキュルキュル音の見分け方は?
- 2.0.6 Q6. ウォーターハンマー(配管のカーン音)と関係ありますか?
- 2.0.7 Q7. エコキュートでもキュルキュル音は起きますか?
- 2.0.8 Q8. 異音がするがエラーコードは出ていない。依頼の目安は?
- 2.0.9 Q9. フィルター清掃の頻度はどのくらい?
- 2.0.10 Q10. 修理と本体交換、どちらが得ですか?
- 2.0.11 Q11. 隣家に響くほどの共鳴がある。自宅でできる配慮は?
- 2.0.12 Q12. どこに点検を依頼すればいい?何を伝える?
給湯器の異音(キュルキュル)の原因と見分け方
症状の特徴と危険度の目安

「キュルキュル」は一般に、回転部の軽い摩擦音や配管・筐体の共振が主因とされ、一定の湯量・温度・風向など特定条件でのみ再現するのが特徴です。まず着目したいのは、①音の質(擦過音・甲高音・振動音)、②継続時間(断続/持続)、③発生タイミング(着火直後・停止時・一定流量時)、④随伴症状(黒煙・ガス臭・焦げ臭・リモコンエラー・湯量/温度不安定)の4点です。これらのうち随伴症状が一つでもあれば安全側に倒して使用中止が原則となります。逆に、仕様範囲の作動音(ファンの風切り音や凍結予防運転の短い駆動音など)と見分ける手掛かりは、音が「条件を外すと直ちに消えるか」「音量が徐々に悪化していないか」です。金属的で鋭い連続音、ボンッという衝撃音、燃焼時の空気不足を示唆する匂い・煙は高リスクの兆候と捉え、換気確保のうえ点検を依頼します。軽度の擦過音のみで湯量・温度が安定しエラー表示もない場合は、配管固定の緩みやフィルター詰まりなどの軽微要因から切り分けます。ただし、軽症に見えてもベアリング摩耗や弁作動不良が進行しているケースはあり、再現条件と音の推移(録音・メモ)を整理して早期に専門業者へ共有することが、二次被害の回避につながります。なお、本体カバー内へのアクセスやガス系統の調整は危険を伴うため、自己判断では行わないでください。
- 高リスクの代表例:黒煙・ガス臭・焦げ臭/爆発的な着火音/異常な発熱/エラー表示
- 中リスク:運転条件に関係なく持続する甲高音や強い振動(摩耗・共振の進行疑い)
- 低リスク:特定条件のみの軽い擦過音(まずは固定・清掃・操作習慣の見直し)
危険サインが一つでも該当する場合は運転停止が原則です。換気を確保し、専門業者やメーカーサポートへ連絡してください。
判断のコツ:音質+随伴症状+再現条件の3点セットで記録し、危険サインがあれば停止・換気・連絡。
シャワー時だけ鳴る原因

シャワー使用時は、節水機構やサーモ混合栓の調温制御、こまめな開閉操作により水圧・流量が細かく変動します。すると、流量センサーや逆止弁、減圧弁といった可動部で微小な振動が生じ、固定が甘い配管や本体筐体と共振して「キュルキュル」と知覚されやすくなります。さらに、シャワーヘッドや混合栓内部のストレーナー(微細なゴミを捕集する金網)の目詰まりは流路を狭め、局所的な圧力上昇やキャビテーションに近い現象を招いて高周波音を助長します。止水時の急閉も要注意で、配管内に圧力波が発生(ウォーターハンマー)し、金具や壁体がビビりやすくなります。
まずは分解を伴わない範囲の安全な確認から着手します。①シャワーヘッドと混合栓のストレーナーを取り外して流水で清掃し、異物・カルキの付着を除去。②シャワーヘッドの切替(強/節水/ミスト等)を変えて音の変化を観察。③混合栓の操作は緩閉を意識し、急閉を避ける。④露出配管・金具の触診でガタつきや壁との接触点を特定し、可能な範囲でクランプの増し締め・防振材の挟み込みを行う。⑤給湯器側の給水フィルター(外部から着脱できる網)の清掃で流量を回復させる。これらで改善しない場合、混合栓カートリッジの摩耗、減圧弁の不調、内部ポンプ・ファンの鳴きなど機器側の要因が疑われます。複数の吐水口(台所・洗面・浴室)で再現性を比較すると切り分けが進み、シャワーのみで発生するなら水栓・配管側、全吐水口で発生するなら給湯器本体側の可能性が高まります。なお、元栓や止水栓を大きく調整する操作は水圧・給湯性能に影響し、他設備へ波及するおそれがあるため、自己判断での常用は避け、異音の記録を添えて点検を依頼してください。
節水シャワーは流量が少なく圧力が高くなりやすい製品があります。試験的に通常吐水に切り替えて音が減るか確認すると原因の手掛かりになります。
追い焚き・湯はり時の原因

追い焚き・自動湯はりで目立つキュルキュルは、浴槽の循環回路を通る循環ポンプのベアリング摩耗や羽根車の微小欠け、浴槽配管のエア噛みが主因として挙げられます。循環口のフィルターに皮脂・繊維・入浴剤成分が付着すると吸込みが偏り、流量が周期的に揺れて高周波の流体ノイズが発生します。さらに、配管勾配が不適切だったり配管内に微細な気泡が滞留しやすいレイアウトだと、運転の度に気泡が出入りして「ヒュルヒュル/キュルキュル」が強調されることがあります。凍結予防運転や自動保温のタイミングで短時間だけポンプ音が強まるのは仕様の範囲に含まれる場合がありますが、以前より音量が増した、あるいは持続時間が延びたと感じる場合は劣化のサインと受け止めます。
自分でできる対処は、①循環口フィルターの取り外し清掃(柔らかなブラシと流水で付着物を除去し、確実に復旧)、②循環口周りにタオルや洗面器などが触れていないかの確認、③浴槽水位が循環口を十分に覆っているかの確認、の3点が基本です。改善しない場合は、循環ポンプの摩耗や弁作動不良、配管内スケール付着が疑われ、分解・部品交換・洗浄(薬剤や高圧は要専門判断)が必要になります。長期的な再発防止には、入浴剤の使用量・種類の見直し、定期的な配管洗浄(取扱説明書の指示に従う)と、設置環境の点検(支持金具の緩み・共振点の有無)が有効です。マンションなどでPS(パイプスペース)内に本体がある場合、躯体の共鳴で音が室内に増幅されることがあり、防振材の追加や固定方法の見直しが効果を示すことがあります。いずれも安全確保を優先し、内部に手を入れず、症状の録音・発生条件の記録を添えて専門業者へ相談してください。
冬だけ異音が増える理由

冬季にキュルキュルが強まる背景には、配管内の水温低下と外気条件の変化が重なります。水温が下がると粘度・密度が上がり、同じ水栓開度でも実流量や圧力損失が変化し、流量センサーや弁の作動点がずれて共振条件に入りやすくなります。燃焼制御側でも着火・安定燃焼までの制御が相対的にシビアとなり、ファン回転数の上昇や制御の微調整が増え、境界条件で高周波の擦過音・流体音が出やすくなります。さらに屋外設置では、北風やビル風の乱流が排気に巻き込み、排気フードやダクトの共鳴を誘発し、金属板・樹脂カバー・配管がビビりやすくなります。凍結・融解を繰り返す環境ではパッキンや支持材が硬化・痩せを起こし、微小な隙間流れや固定の緩みが音源化します。これらは単独では小さい現象でも、条件が重なると可聴域で「キュルキュル」にまとまって知覚されます。
対処は「設置環境」「流体条件」「固定・防振」の三方向から同時に行うのが効果的です。設置環境では、風の直撃を避ける配置の見直しや簡易の防風板(安全を損なわず排気・吸気を妨げない形状)で乱流を抑えます。流体条件では、節水シャワーや末端フィルターの目詰まりを清掃して不必要な圧力上昇を避け、極端な高温設定・低流量運転を見直して共振域を外します。固定・防振では、露出配管の支持間隔を適正化し、クランプ増し締めや防振ゴムの更新、配管と外壁が接触する箇所への当て物でビビりを吸収します。凍結が疑われる地域は、保温材の破れ・隙間の補修と、取説に沿った凍結予防運転の確認が有効です。季節要因で増える異音は、環境と運転条件の調整で低減できる場合が多く、以前より音量・頻度が悪化しているなら、内部劣化の進行を疑って点検を検討します。
ファン作動音との違い

正常なファン作動音は「ブーン」と連続する回転音が中心で、運転開始直後の吹き上がりや燃焼負荷の変化に応じて緩やかに音量・音色が変化します。これに対し故障寄りのキュルキュルは、高周波で金属的・擦過的に聞こえ、特定の回転数・流量帯で突然立ち上がる性質があります。回転に同期して「周期的に強弱を繰り返す」「角度を変えると局所的に鋭く聞こえる」といった特徴は、ベアリングの乾き・摩耗、ファンケーシングやダクトとの微接触、異物の軽接触など機械的要因を示唆します。風向・風速の影響で音が増減する場合は風の巻き込みによるフード・ダクト共鳴の疑いが高く、運転場所や外気条件を変えた比較試験が切り分けに有効です。また、電装系のPWM(回転制御)由来の軽い高周波成分は仕様上のこともありますが、時間とともに大きくなる・異臭や異常振動を伴う場合は要点検です。
ユーザーが安全にできる観察としては、①運転直後・安定運転・停止直前の各フェーズで音質の変化を録音し、②排気口近傍・本体正面・配管取り出し部など複数地点で聞き比べ、③外気条件(風の有無・気温)と音の相関をメモする、の三点が有効です。鋭い金属音が徐々に増大する、低い振動が床や壁に伝わる、回転数に比例して音が上がる、といった兆候は早期の部品交換で静音性と安全性を取り戻せる可能性があります。一方、正常音か故障音かの判断に迷うケースも多く、無理に潤滑剤を噴霧したりカバーを外したまま運転するのは厳禁です。ファン関連は燃焼・排気安全に直結するため、異音が明確なら録音と観察メモを添えて点検を依頼してください。周辺設備(レンジフード等)の同時運転が負圧を作り音質を変える場合もあるため、同時運転の有無も記録しておくと切り分けが速くなります。
ウォーターハンマーの可能性

ウォーターハンマー(水撃作用)は、水を流している配管を急閉したときに圧力波が往復する現象で、「カーン」「キーン」といった甲高い音や振動、配管のビビりを誘発します。給湯器の近くで顕著に感じる場合、元々の水圧が高い、緩閉機能の弱い水栓を使用している、配管の支持間隔が広い・固定が甘い、減圧弁が不調または未設置、といった条件が重なっていることが多いです。また、節水機構で流路が細いシャワーヘッドや目詰まりしたストレーナーは局所的な圧力上昇を招き、閉止時の圧力波を強めます。ハンマーが強いほど、弁・センサー・継手に衝撃が繰り返し伝わり、長期的な部品劣化のリスクも増します。音の再現は「水を強めに流した後、急に止める」「別の吐水口を同時に開閉する」などで起きやすく、発生の有無・強さ・配管のどこで響くかを観察することで原因特定に近づきます。
対策の基本は、①操作習慣の見直し(急閉を避けて緩閉する)、②末端側の清掃(シャワーヘッド・水栓ストレーナーの洗浄)で余計な圧力上昇を抑える、③配管支持の適正化(クランプ追加・防振材挿入・外壁との離隔確保)、④設備側の調整・更新(減圧弁の新設/交換・適正圧設定、緩閉式水栓への更新、水撃防止器〈アレスタ〉の導入)という段階的アプローチです。特に集合住宅や高水圧エリアでは、元圧を適正化する減圧弁と緩閉水栓の組み合わせが有効で、施工には現場状況の確認と計算が必要です。水撃防止器は設置位置(衝撃源に近い枝管)と姿勢(縦設置推奨)が重要で、誤った位置では効果が限定的になります。いずれも専門知識を要するため、自己施工は避け、記録した再現条件と音の性状を共有して設備業者に相談してください。適切な対策が取られれば、キュルキュルやキーンといった二次的な共振音もまとめて低減できることが多いです。
配管の共振・固定ゆるみ

配管や本体金具のわずかなガタつきは、運転中に生じる振動(ポンプ・ファン・弁の切替、流速の変化、外風)と結び付くと、壁・床・天井などの構造体を巻き込んで増幅され、「キュルキュル」「ビビリ」に変換されます。特に屋外壁掛けやマンションPS内の設置では、支持金具や配管の支持間隔、外壁材の剛性、配管が壁面や金属部に触れているかどうかが支配的です。配管はS字や急激な方向転換の箇所で固有振動数が下がり、細い金属管や保温材が痩せて隙間ができた箇所は接触音が出やすくなります。まずは露出して見える範囲のみで点検を行い、クランプ・吊りバンドの緩み、配管が壁や機器カバーに当たっている箇所、保温材の破れ・偏摩耗を探します。触診で軽く押したときに音が止む箇所があれば、そこが共振点の手掛かりです。改善は「支持の追加・位置の最適化」「接触の解消」「振動の減衰」の三段階で考えます。具体的には、支持金具の増し締め、支持間隔の短縮(長すぎるスパンを詰める)、配管と壁の間に不乾化タイプの防振材や耐候性のゴムスペーサーを挟む、保温材の欠損部を補修して剛性と緩衝を回復する、などが低リスクで有効です。なお、排気経路や燃焼空気の通路に影響する加工、カバーを外したまま運転する行為、躯体に過大な穴あけ・ねじ込みを行うことは安全上不適切です。共振は複合要因で起こるため、一点だけで完治しない場合がありますが、「触ると止む箇所」→「支持を追加」→「接触を避ける」→「減衰材で仕上げる」の順で段階的に潰していくのが合理的です。PS内では躯体全体が鳴ることがあり、扉・点検口のパッキン交換や、扉内側に薄い防振シートを貼るだけで室内側の聴こえ方が大きく改善するケースもあります。作業は必ず通水・通ガスに影響しない範囲で行い、固定金具やボルトの脱落・過締めによる破損を避け、難しい場合は業者に現地で最適ポイントを選定してもらいましょう。
- 優先度:緩みの是正 → 接触点の排除 → 支持間隔の適正化 → 防振材で最終調整
- 材料の目安:耐候ゴムスペーサー、低反発系防振テープ、保温材補修用スリーブ
- 避けること:排気フードの塞ぎ・改造、可燃物の近接、過度な穴あけやアンカーの乱用
給湯器の異音キュルキュル対策
まず自分でできる安全確認

安全を最優先に、分解を伴わず外側から実施できる範囲に限ってチェックします。①安全確保:窓を開ける・換気扇を回す。ガス臭・焦げ臭・黒煙・異常発熱があれば直ちに運転停止。②情報の整理:リモコンのエラー表示有無、型番・製造年(銘板)、設置場所(屋外壁掛け・PS内など)を控える。③再現条件の記録:発生する蛇口、時間帯、設定温度、湯量、外気条件(風・気温)をメモし、スマホで短い録音/動画を残す。④視認できる異物の除去:排気口周辺の枯れ葉・虫の巣・ビニール等を除去(排気路を変形させない)。⑤末端側の清掃:シャワー・水栓のストレーナーを外して流水洗浄、給湯器の給水フィルター(外部から外せる網)を掃除し、確実に復旧。⑥配管と金具の触診:露出配管を軽く押さえ、当たりやガタつきが音に影響するか確認(熱い場合があるため手袋推奨)。⑦試験的な条件変更:節水モードや極端な低流量・高温設定を一時的に避け、緩閉操作で音の変化を確認。
以上で「危険サインなし+軽度の音」の場合、しばらく観察しつつ記録を蓄積します。改善が乏しい、あるいは音が増大する場合は、無理をせず点検依頼へ。依頼時は、型番/設置年/発生場所/再現条件/録音・動画リンク/実施した清掃内容のセットを共有すると一次対応が速くなります。なお、屋外作業時は濡れた足場・雨天での作業を避け、通電部・ガス配管・排気部に触れないことが原則です。工具を使わずに外せる部品(フィルター・カバーの一部)以外には手を入れず、強い力でねじを回さないでください。集合住宅では、夜間の試験運転が近隣迷惑になることがあるため、時間帯配慮も重要です。
点検依頼に役立つ持ち物:型番写真/異音の録音/発生条件メモ/エラー表示の写真/設置全景の写真(排気口や周辺の距離感が分かる構図)
絶対にやってはいけないこと

燃焼機器・加圧配管を含む設備のため、誤った対応は事故や故障の拡大につながります。以下は厳禁です。①内部の分解・改造:本体カバー内部(燃焼室、電装、ガス通路、熱交換器)へのアクセス、基板の調整や配線いじり、センサーや安全装置のバイパス。②ガス・排気系への介入:ガス圧やノズル、バーナーの自己調整、排気ダクトの短縮・折り曲げ・塞ぎ、排気フードにネットやカバーを強引に追加。③薬剤や潤滑剤の無差別噴霧:ファン・ポンプ・弁へ油や溶剤を吹き込む行為(可燃性蒸気・樹脂劣化・ホコリ付着の原因)。④温度ショック:凍結時に熱湯をかける、火で炙る。⑤非適合部材の使用:屋外用でないテープやスポンジ、防火・耐熱要件を満たさない緩衝材を排気周りに貼る、結束バンドで強引に固定。⑥通水・通電中の無理な作業:濡れた手での操作、足場不良での作業、雨天での電装付近の点検。⑦無資格工事:減圧弁の新設や水撃防止器、ガス接続の変更、配管切回し等の施工。これらは感電・漏水・ガス漏れ・一酸化炭素中毒・火災の重大リスクを伴います。音が気になると潤滑剤や消音材で「とりあえず抑える」対処に走りがちですが、根本原因の隠蔽は故障の深刻化や保証の失効を招きます。判断に迷う場合は、異音の記録と実施済みの清掃内容を添えて相談し、安全装置と排気経路に影響する作業は一切行わないことを徹底してください。
「カバーを外したままの運転」「排気口の塞ぎ」「ガス圧の自己調整」は重大事故の主因になり得ます。いずれも絶対に行わないでください。
フィルター清掃と流量回復

キュルキュルの背景には、末端や本体のフィルター目詰まりによる「流量の不安定化」が潜んでいることがよくあります。流路が狭まると、一定の流量を保とうとする制御が小刻みに介入し、弁やポンプに微振動が伝わって高周波音が立ちやすくなります。対処の第一歩は、分解を伴わない範囲でのストレーナー清掃です。対象は①シャワーヘッドや混合栓のストレーナー、②給湯器本体の給水フィルター(一般に外部から取り出せる網状部品)、③追い焚き配管の循環フィルターの三つ。手順は共通して、止水→残水受けの準備→フィルター取り外し→流水洗浄→パッキン・向きの確認→確実な復旧→開栓後の漏れ確認、の順で進めます。特にOリングやパッキンの座り、フィルターの向き(表裏)を誤ると、漏れや異音悪化の原因になります。カルキや砂、細かな繊維くず、入浴剤成分が付着している場合は、柔らかいブラシでやさしく落とし、溶剤や油は使いません。清掃後は、湯量が増えたか、温度の上下が落ち着いたか、異音が弱まったかを確認し、改善の有無を記録します。
浴室側の循環フィルターは、皮脂や繊維が溜まりやすく、吸込みが偏るとポンプ入口で気泡が発生し、キャビテーション様のノイズを伴うことがあります。入浴剤を頻用する家庭では、清掃周期を短く設定すると再発予防に有効です。井戸水や工事後などで微細な砂が混入しやすい環境では、目詰まりの再来が早い傾向があるため、清掃と観察をセットで回すことが大切です。あわせて、混合栓やシャワーヘッドの節水モードを一時的に解除して音の変化を確認すると、過度の絞り込みが原因かどうかの切り分けに役立ちます。なお、清掃で改善が見られない、または短期間で再発する場合は、弁の作動不良やポンプ・ファンの摩耗、熱交換器のスケール付着など、内部要因の可能性が高まります。これらは分解・調整を伴うため自己対応は避け、記録(発生条件・録音)を添えて点検を依頼しましょう。外装ビスの過度な増し締めや、排気周りに市販のネット・カバーを追加する行為は風路を乱して逆効果になるため厳禁です。清掃は「元に戻す自信がある箇所だけ」を徹底し、無理を感じた時点で手を止める判断が、結果として最短の解決につながります。
減圧弁・緩閉水栓の導入

ウォーターハンマーや共振が疑われるケースでは、設備側の見直しとして減圧弁(PRV)と緩閉水栓の導入が有効です。減圧弁は建物や系統の静圧・動圧を安定域に落とし込み、閉止時の圧力波(ハンマー)を和らげます。緩閉水栓は、レバー操作の終端で水路をゆっくり絞ることで圧力変動の立ち上がりを鈍らせ、弁・配管・機器に伝わる衝撃を低減します。導入の前には、現場の圧力をゲージで計測し、昼夜や同時使用時のばらつきを把握することが重要です。集合住宅では建物全体の系統設計が影響するため、管理組合・管理会社との調整が必要な場合があります。設置位置は、元栓直後で全系統をカバーする方法と、問題が顕在化している枝管(給湯器手前など)を狙う方法があり、効果と施工性のバランスで判断します。配管の支持間隔やクランプの状態、配管材質(樹脂管・銅管・鋼管)もハンマーの伝播に影響するため、減圧弁単体ではなく、支持の適正化+緩閉水栓+水撃防止器(必要時)の組み合わせで最適化するのが定石です。
注意点として、減圧弁には適正な設定圧と定期点検が必要で、設定を闇雲に下げると、同時使用時に湯量不足や着火不良が起きることがあります。また、緩閉水栓はユーザーの操作感に影響するため、家族の使用習慣に合う製品を選ぶことが大切です。水撃防止器(アレスタ)は、衝撃源に近い位置に縦姿勢で設置すると効果が出やすい一方、系統の空気溜まりやドレンの設け方を誤ると性能が落ちます。いずれも配管切回しや加圧系統に関わる工事であるため、自己施工は避け、資格を持つ設備業者に現地調査と計算(静圧・動圧・同時使用条件)を依頼してください。導入後は、閉止時の音の推移、着火の安定度、同時使用での湯温変動といった評価項目をチェックリスト化して比較すると、対策の妥当性が検証できます。適切にチューニングできれば、キュルキュルやキーンといった二次的な鳴きも同時に弱まり、機器寿命の面でもメリットが期待できます。
修理費用相場と交換判断
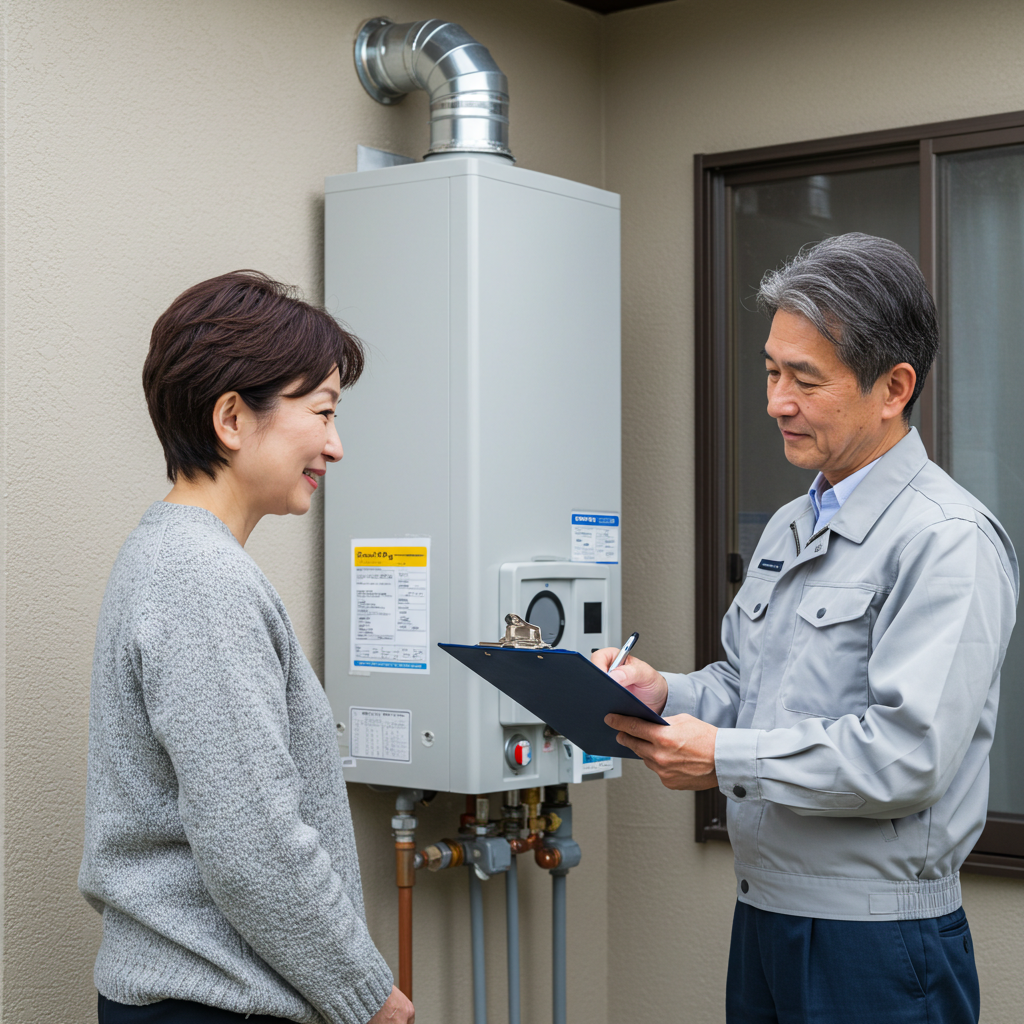
費用は「故障部位」「機種・方式」「設置条件」「出張距離・時間」「部品供給状況」で大きく振れます。一般に、循環ポンプやファンモーターなどの回転部品は部品代+作業で数万円規模、減圧弁・弁周りの調整や交換は数万円前後、配管の固定・防振の軽作業は1万円未満〜数万円、本体交換は機種・工事範囲により十数万〜数十万円が目安です。見積もりでは、①症状の原因仮説と再現条件、②交換部品名と品番、③部品・作業・出張・処分など費目の内訳、④保証(部品・工事)の期間、⑤追加発生し得る作業の有無と条件を明示してもらいましょう。同じ症状でも解の取り方が複数あるのが設備の常で、例えばポンプ交換で解決するケースもあれば、配管支持の是正+減圧で十分な場合もあります。2〜3社で比較し、「なぜその作業が必要か」「代替案は何か」を質問すると、費用対効果の見通しが立ちます。
交換判断は、①使用年数と部品供給期限、②主要部品の複数劣化(ポンプ+ファン+弁など)、③安全関連の不安(燃焼・排気・漏水)、④静音性や省エネなどの体感メリット、の四軸で検討します。部品供給が難しくなる年数を過ぎ、修理のたびに待機や費用が嵩むなら、総所有コスト(LCC)で見ると更新が合理的となることが多いです。更新時は、既存配管の状態(勾配・支持・材質)、設置環境(風の当たり、PS内の共鳴)、水圧条件(減圧弁の有無)、同時使用のニーズ(浴室+台所など)も合わせて是正すると、異音の再発防止と快適性の底上げにつながります。工事内容の確認ポイントとして、旧機撤去・産廃処分の費用含有、ガス可とう管・フレキの更新、試運転と漏れ・排気の安全確認、操作説明の実施、保証書の発行、アフター窓口の明示をチェックリスト化して受け取りましょう。短期の最小修理に惹かれやすい場面でも、安全・静音・可用性の三要素を総合評価して選択することが、結果的に満足度の高い解に近づきます。
| 症状・作業例 | 主な内容 | 目安費用(税込) | 交換検討の目安 |
|---|---|---|---|
| 循環ポンプ異音 | 循環ポンプ交換・エア抜き | 25,000〜55,000円 | 他部位も劣化・年数8年以上 |
| ファンモーター鳴き | ファンモーター交換・調整 | 20,000〜45,000円 | 熱交換器劣化と併発時 |
| 弁作動音・共振 | 減圧弁点検・交換、調整 | 15,000〜35,000円 | 配管改修が必要な場合 |
| 配管固定・防振 | クランプ追加・防振材施工 | 8,000〜25,000円 | 外壁・躯体の共鳴が大きい |
| ストレーナー詰まり | 清掃・流量調整 | 0〜8,000円 | 再発多発・他症状併発 |
| 本体交換 | 同等機種への更新工事 | 120,000〜300,000円 | 年数10年以上・主要部品複数劣化 |
費用は一例です。実際の価格は現場条件や部品供給、作業時間によって変わります。見積時は「型番・設置年・症状の再現条件」を共有してください。
まとめ 給湯器の異音キュルキュル
- キュルキュルは共振摩耗流量不安定が重なり条件次第で顕在化
- 危険サインがあれば運転停止換気確保点検依頼を最優先
- シャワー時は流量変動で弁や配管が共振し音が強く現れる
- 追い焚き時は循環ポンプ摩耗やエア噛みを重点的に切り分け
- 冬季は低水温と外風で共鳴が起きやすく環境調整が有効
- 正常なファン音は一定で高周波の突発音は故障疑いが高い
- 急閉操作は水撃を招き配管や弁を振動させ異音を増幅
- 露出配管の固定緩みや接触点は支持強化と防振材で是正
- 自分で行う作業は外観確認とフィルター清掃に限定する
- 排気口の異物除去と周辺の可燃物排除で燃焼安全を確保
- 節水機能や目詰まりが圧力上昇を生み異音の温床となる
- 井戸水や工事後は微細な砂で再発しやすく清掃周期短縮
- 記録した型番設置年再現条件録音動画が診断を加速
- 無資格での分解改造や薬剤噴霧は故障拡大と安全低下
- 減圧弁緩閉水栓水撃防止器は系統条件を踏まえ業者対応
よくある質問(FAQ)
Q1. 給湯器のキュルキュル音は放置しても大丈夫?
A. 軽度で一時的な場合でも、摩耗や共振が進むと悪化するおそれがあります。黒煙・ガス臭・焦げ臭・爆発的な着火音・エラー表示のいずれかがある場合は直ちに使用を中止し、換気のうえ点検を依頼してください。
Q2. まず自分で確認できる安全な対処は?
A. 排気口まわりの異物除去、シャワーや水栓のストレーナーと給湯器給水フィルターの清掃、露出配管・支持金具のガタつき確認、急閉を避けた操作が安全範囲です。内部の分解・調整は行わないでください。
Q3. シャワーのときだけキュルキュル鳴るのはなぜ?
A. 節水機構やサーモ混合栓による流量変動で、弁や配管が共振しやすくなるためです。ストレーナー清掃と緩閉操作で改善することがあります。改善しない場合は減圧や水栓カートリッジの摩耗などを点検します。
Q4. 冬だけ異音が増えるのは故障?
A. 低水温・外風・凍結予防運転など季節要因で共振条件に入りやすくなることがあります。保温材の補修、防風配慮、設定や流量の見直しで低減する場合がありますが、悪化が続くなら点検を受けてください。
Q5. 正常なファン作動音と故障のキュルキュル音の見分け方は?
A. 正常音は一定の「ブーン」。故障寄りは金属的で高周波・条件依存の立ち上がりが特徴です。回転に同期して強弱する、時間とともに大きくなる、異臭や異常振動を伴うときは早めに点検が必要です。
Q6. ウォーターハンマー(配管のカーン音)と関係ありますか?
A. 急閉や高水圧で生じる水撃が、弁や配管、筐体を振動させてキュルキュルやビビリ音を誘発することがあります。緩閉水栓・減圧弁・配管支持の最適化・水撃防止器の導入が代表的対策です(施工は業者へ)。
Q7. エコキュートでもキュルキュル音は起きますか?
A. ヒートポンプや循環系のポンプ・弁・配管の条件が揃うと発生することがあります。加圧・循環系のフィルター清掃と配管支持の見直し、運転モードや湯温・流量の調整で改善することがあります。
Q8. 異音がするがエラーコードは出ていない。依頼の目安は?
A. エラーなしでも、音が継続・増大・範囲拡大する、季節を越えて続く、他症状(湯温不安定・着火不良)がある場合は点検推奨です。録音と発生条件(時間帯・湯温・流量・風)を添えると診断が速くなります。
Q9. フィルター清掃の頻度はどのくらい?
A. 使用状況によりますが、月1回程度を目安に。入浴剤頻用・井戸水・工事後などは短いサイクルで。清掃後は湯量・温度安定・音の変化を確認し、効果が薄い場合は内部要因を疑って点検を検討します。
Q10. 修理と本体交換、どちらが得ですか?
A. 使用年数、部品供給、劣化部位の数、静音・省エネの期待値で総合判断します。年数10年前後で主要部品が複数劣化・修理が重なる場合は、総所有コストの観点で交換が合理的になることがあります。
Q11. 隣家に響くほどの共鳴がある。自宅でできる配慮は?
A. 使用時間帯の配慮、急閉の回避、露出配管の支持強化・防振材の追加、PS扉のパッキン補修などが有効です。根本対策は設置環境と配管支持の最適化になるため、現地診断を受けると確実です。
Q12. どこに点検を依頼すればいい?何を伝える?
A. メーカーサポートまたはガス事業者・設備業者へ。型番・設置年・設置場所、発生場所(どの吐水口)と再現条件、録音・動画、実施した清掃内容、エラー表示の有無をセットで伝えると対応がスムーズです。
参考・出典
-
経済産業省「ガスを安全に利用する4つのポイント」ほか広報資料
- ガス機器使用時の換気や給気・排気部の確保、一酸化炭素中毒事故防止についての注意喚起資料。 -
公益財団法人 給水システム協会「配管についてQ&A(ウォーターハンマーとは)」
- 水撃作用(ウォーターハンマー)の仕組みと、騒音・配管への影響、防止策(緩閉操作や水撃防止装置)に関する解説。 -
リンナイ「メンテナンスについて(給湯器の凍結予防と対策)」
- 給湯器のメンテナンス方法や凍結時・凍結予防時の正しい対処法(熱湯をかけないこと等)を示したメーカー公式情報。
タグ:トラブル・修理



















